内容説明
危機の時代、先の見えない時代において、ほんとうに必要とされ、ほんとうに信じられる知性・教養とはなにか? それは、視界の悪い濃霧の中でも道を見失わずにいられる「方向感覚」のこと。複雑性の増大に耐えうる知的体力をもち、迷ってもそこに根を下ろしなおすことのできるたしかな言葉と出会う。社会、政治、文化、教育、震災などの領域において、臨床哲学者がみずからの方向感覚を研ぎ澄ませながら綴った思索の記録。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
58
敬愛する鷲田先生の言葉。鷲田先生の言葉は、何故、こんなに穏やかでありながら、深くて、鋭くて、思いやりに溢れているのだろうかと思う。今のこの国を覆っている、停滞と殺伐とした空気の中で、ほんのりと先を照らしてくれるようだ。日々の営みの中で綴られた言葉は、まさに、生きる哲学でもある。自分自身の在り様を再確認するには、鷲田先生の言葉は最適だと思っている。2022/06/03
よこたん
52
“標準語で書かれた端正な文章を読んでいても、書いているのが関西人ではないかとおもうときがある。” ああ、これか。鷲田さんの文章がとても好きな理由が分かった気がした。なかなかにかたい内容のことでも、どことなく柔らかな物腰というか、温かみがあるというか。この多幸感が、どこから来るのかが、ストンと腑に落ちた。「社会」「政治」は悲しいかな頭がついていけなかったが、「文化」「教育」はそうそうと楽しく、「身辺雑記」は一番面白かった! 「震災後のことば」は、胸の中を風がぴゅうと吹き抜けるような心地だった。2019/05/09
抹茶モナカ
24
朝日新聞一面の『折々のことば』を毎日チェックしているので、著者が引用する箴言とそこから導く哲学には親しみがあり、新聞の片隅のコーナーからより大きく入れ物を変えての思考を味わえた。この哲学エッセイ集で一番強く考えさせられたのは、公共サービスへの依存で生きる力を失った私達日本人の事。東日本大震災の際には、或いは、自分たちは難民になっていたかもしれない事。繰り返し語られていたせいもあり、ハッとさせられた。幾つかのテーマ毎に分けられているエッセイ集で、哲学のエッセンスがあって、短いエッセイが主なので読みやすい本。2019/05/01
ムーミン
23
「つくる」と「つかう」の話、とても心に残りました。「つくる」ことが、人の普段の暮らしから離れていった。「つかう」とは、道具に「付く」「合う」こと。自らと道具とが一つとなり、道具が自分の体の一部となって対象に働きかけること。2019/05/13
ERIN
5
タイトルが秀逸…!と思って手に取った。現代ではいつの間にかサービスを享受することが当たり前で、自分で作ったり考えたりする力がどんどん弱くなっている。自分のサイズや立っている場所を知って、自分で制御できるサイズの経済行為を保持しておくこと、仕事における納得感(作業自体が楽しい×誰かの役に立っている)、平衡感覚、性急さから距離を取ってじっくり取り組むことを自分に許してあげること、大事だ。2025/09/08
-
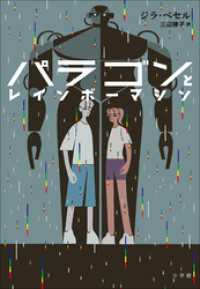
- 電子書籍
- パラゴンとレインボーマシン SUPER…
-
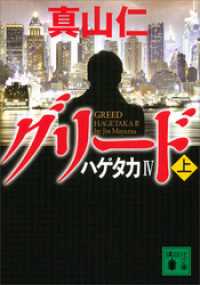
- 電子書籍
- ハゲタカ4 グリード(上) 講談社文庫







