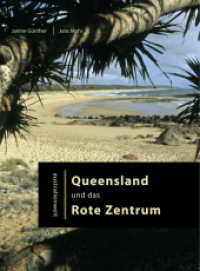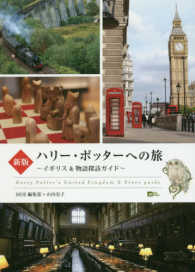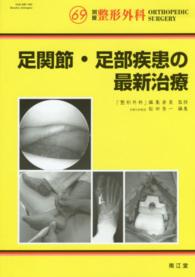内容説明
通貨、とりわけ「銭」に注目し、信長~家康期の貨幣統合過程の足跡を辿り、中世と近世の転換点を探る。カネという社会通念を軸にしてはじめて見えてくる戦国・江戸期の実態に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
47
どうしても必要な通貨を政府が発行しなかったために、やむをえず輸入したり、民間が作って流通させたのが「ビタ銭」。けっして現代的な意味のニセ金ではなかった。とにかく中世の「お金」の常識をくつがえすような論が満載。紙幣の出現も、ただひとつ、一文という単位の硬貨しかなかったため、昔の人の知恵が生んだ合理的な解決法。ここには決して莫迦に出来ないものがある。2018/12/20
ゲオルギオ・ハーン
26
戦国時代の貨幣について調べるために読みました。面白いのは銭の使われ方については幕府や大名が主導したわけではなく、民間での使われ方を尊重し、追認しながら秩序づくりをしていたという視点が面白いし、納得できる。当時の統治制度的に現代的な貨幣使用の取締ができるはずもないことは分かる。つまり、市場に受け入れられるルールを出せるか、武士たちの収入を守れるか(権力を支えている武士たちの生活を守ることが大名たちの死活問題でもある)ということが戦国大名たちの経済的課題になってくると推測される。2023/08/03
鯖
21
清盛の宋銭に始まり、大陸の銭に貨幣経済を依存していた日本。しかし明の鎖国政策の影響で、東アジア全体に銭が不足する。ないなら作るしかないので、民間が中国の銭をまねてビタを作り始めた。それに伴い、撰銭が起こる。ビタは受け取れないと大陸の銭を選択する。次に階層化が起こる。例えばビタ千文は本銭500文の価値しかないと。古い銭を撰る理由として最近でも二千円札はちょっと胡散臭くてみんな忌避してたでしょ…と著者が例示してたのがなるほど納得。2021/01/01
浅香山三郎
20
『貨幣の日本史』(中公新書)も面白かつたが、本書も著者の専攻する日本中・近世史の話だけあつてたいへん面白い。近年の考古学、歴史学を始め、中国などの東アジア情勢をも踏まへた視野の広さを生かして議論を展開する一方、時期や地域の銭貨流通の状況からかなり原理的にときどきの政策意図を読み解く力量に敬服する。社会経済史は単なる史料解釈のセンス以上に、原理的思考の巧みさが勝負どころだといふことがあらためて感じられた。2020/11/07
MUNEKAZ
10
地域ごとに流通する貨幣が異なる中世から、信長・秀吉らによる「ビタ」の統一、そして江戸幕府の三貨制度へと至る流れを紹介した一冊。著者はこの一連の動きを天下人たちに何らかのグランドデザインがあったわけではなく、むしろ民間の動きを追認するものであり、またあくまで軍事的な動機で行われていたことを強調している。他にも永楽通宝が畿内では嫌われ、東国では好かれたなど地域ごとのえり好みの話も興味深かった(ならば信長は嫌われ銭を旗印に上洛したのかと…)。2018/09/02
-
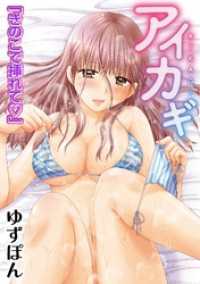
- 電子書籍
- アイカギ【単話】(154) モバMAN