内容説明
日本の失われた1カ月とは?! 西暦は実は二の次?! 世界から7年遅れてる国がある?!
宗教・アート・食文化・仕事……
カレンダーから見える意外な事実!
普段生活するなかで当たり前のように使っている暦。ですが、歴史を勉強してみたり、海外へ旅行してみると、はじめて知る暦の不思議がたくさん出てきます。暦にまつわる不思議を知れば、日本と世界の文化・暮らしの違いや共通点に気づき、異文化理解も深まります。世界中のカレンダーを収集し、そのカレンダーが使われる地域の社会・文化・暮らしを理解するための研究を長年行ってきた著者が、さまざまな角度から暦の話をわかりやすく語ります。
目次
第1章 暦とは何か
第2章 暦は国によってこんなに違う!
第3章 日本の暦いまむかし
第4章 食と暦の深い関係
第5章 暦から広がるアートの世界
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
22
ないものの例えとして「元年の暦」という言葉があります。改元は突然、年の途中で起きるので、改元された元号を表記した暦はないからです。ところが、2019年は5月の改元が予定され、6月からの半年分のカレンダーが出まわらないとも限りません。前代未聞の「元年の暦」が登場するかもしれません。加えて、日本の法律では元号と皇紀のみが規定され、西暦は事実上の基準でしかありません。『日本書紀』によると神武天皇が「辛酉年春正月庚辰朔」の日に奈良の橿原宮で即位した紀元前660年2月11日を紀元とするのが「皇紀」という紀年法です。2019/02/19
はるぴ@ありがたきハピネス
5
旧暦って、なんかいいよね。失われたものに対する切なさがそう思わせるのか。世界には今もいろんな暦があって、時の流れは変わらないけど、把握の仕方が違うんだな。太陽太陰暦の「閏月」については、Wikipediaの明治三年のカレンダー見るとわかりやすかった。閏月がある年は、だいぶお得感ありそう。それから、アイヌの月の名前の呼び方かわいかった。1月→弓が折れるほど狩りををする月。2月→海が凍る月。3月→日がそこから長くなる月。など。2024/01/31
海星梨
3
文化よりの暦のおはなし。ホライズンカレンダーという知見が得られたのがよかった。最終章はかんっぜんに芸術のはなしでなにも頭に入ってきておりません。以前どこかで読んだような話も多かった。2020/04/09
Shinjuro Ogino
0
後半は暦とは直接関係のない話だが、前半は結構新知識が得られ、面白かった。 ・632年にムハンメドにより採用された太陰暦は、太陰太陽暦を使っていたメッカの既成勢力への対抗意識からだった。ムハンメドの死後、ヒジュラ(聖遷)の622年が紀元とされた(639年)。 ・日本は太陽暦を採用した明治6年に、不定時法から定時法に変更。 ・日本、台湾、北朝鮮の共通点は、1912年を紀元とする年号があること。大正。中華民国暦。1997年制定の主体年号は金日成の生年を紀元とする。 ・ISOの決議で週は月曜始まり。年の週番号。2019/07/05
-

- 電子書籍
- 前略、山暮らしを始めました。6 カドカ…
-
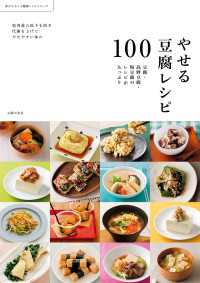
- 電子書籍
- やせる豆腐レシピ100
-
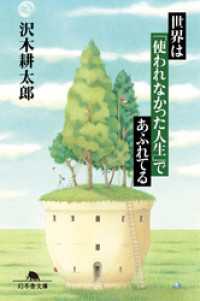
- 電子書籍
- 世界は「使われなかった人生」であふれて…
-
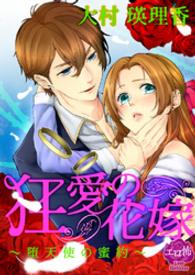
- 電子書籍
- 狂愛の花嫁~堕天使の蜜約~
-
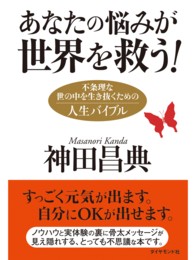
- 電子書籍
- あなたの悩みが世界を救う! - 不条理…




