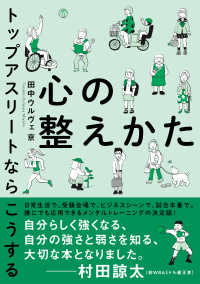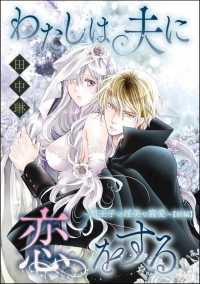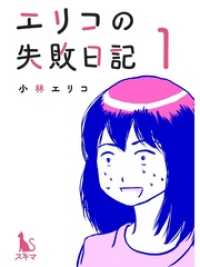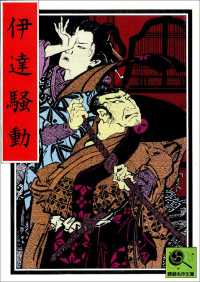- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
◆1989年4月27日、松下幸之助死去。平成元年に高度成長時代を象徴する経営者が亡くなりました。平成の企業経営はどのように変化し、なにを逸脱してしまったのか、失速は宿命だったのか? 本書は、平成30年間の企業経営の軌跡を日本を代表する経営学者が解明するものです。第I部(平成三〇年の日本の産業と企業)では、30年間に日本企業の戦いの軌跡を描きます。崩壊、迷走、回復という3つのステージで何が起きたのかを端的に解説します。第II部(モノ、技術、ヒト、カネ、の三〇年)では各論として日本企業のどのような問題があったのかを解明します。そして日本的経営を愚直に追求してきたトヨタ自動車と、ゴーン改革によって劇的な復活を遂げた日産自動車を比較することで、これからの日本企業に必要な経営の座標軸を示します。
◆著者は平成元年刊行の『ゼミナール経営学入門』(共著)で気鋭の経営学者として実務界でも広く認知され、経営トップとの接点も劇的に増えました。筆者にとって平成の30年とは経営中枢の具体的な情報が得られるようになった時代と言えます。外からの評論家だけではないリアリティを持った分析が可能になっています。本書は、時系列の表面的な経営史を越えた「日本企業失敗の本質」とも言える内容になります。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
58
人本主義を打ち出した伊丹先生の著書。平成を渾身の筆で斬っていて感じ入って平成最後の日に読了。平成の経済的危機は二回あった。 H10年バブル崩壊とソ連崩壊。H20年リーマン危機と民主党不況・東日本大震災。よくこれだけの内外ダメージに日本経済と企業は持ち堪えた。勁草の様だと讃える。それら論は一読の価値あり。ヒトへ変わらぬ基盤を一定温存し、全体的合理性あったと振り返られる。また、我が国得意の複雑系を推し進めよともされる。ただ令和に向かう今、深い傷が癒えてきたが所謂ドツボにハマりつつないか?と警鐘も鳴らす。2019/04/30
Kiyoshi Utsugi
32
平成の日本の経営を振り返ったものです。 第一部 平成30年間の日本の企業 第二部 世界、技術、ヒト、カネの30年 という構成で、第一部では10年を一区切りとして日本の企業を振り返っています。第二部は世界の中の日本企業、技術と産業構造、ヒトのマネジメント、カネのマネジメントという四つの視点で振り返ります。 一番面白かったのは、第二部の一番最後に書かれていたトヨタと日産の章で、まだまだ日本の企業(トヨタだけかもしれませんが)も捨てたもんじゃないなと思いました。2022/07/12
uD
21
日本企業とその経営について平成の30年間を振り返った一冊。使用データが主に財務省の法人企業統計調査故か、30年分の白書を総ざらいした感覚に。①10年区切りという縦糸②4つの要素別という横糸で紡ぐ大きく二部構成。日本企業・日本的経営の基盤の堅牢さの説明を通じて、著者は「日本の未来は明るい」と伝えているように感じた。それは希望的観測かもしれないが、素直に感銘を受けずにいられない。失われた20年とも30年とも言われた平成時代が、間もなく終わりを迎える節目に読むことができてよかった。士業に携わる前に再読したい。2019/04/26
Great Eagle
7
期待もせずに読み始めた本でしたが、中々なものでした。強欲資本主義むき出し経営のアメリカ型と共産党支配の独占巨大企業との競争が本格化する中で、日本は人本主義市場経済を継続させ存在感を打ち出せるのでしょうか。興味は尽きません。この意味で、ROE経営、利益の配当もしくは投資あるいは人件費(労働分配率)適正な配分ってあるのでしょうか。このテーマは、もうしばらくは追っかけていきたいと思います。2019/08/01
GOTI
4
☆☆☆☆なかなか面白かった。平成30年間、バブルが崩壊し金融が崩壊する。そしてリーマンショックや東日本大震災に襲われた日本経済の失速、低迷、再生を自己資本比率、労働分配率、失業率、総資本回転率等々データを駆使しながら克明に活写している。最終章では系列や人に重きを置く所属型人本主義の「強い日本式経営」トヨタとゴーン革命により系列を壊し人を含めたコストをカットしV字回復した欧米風参加型企業日産を比較している。どちらが優っているのかは火を見るより明らかですね。2019/04/24