- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
小売業は日本の経済社会の変化を顕著な形で映し出す鏡。経済成長、人口構造の変化、技術革新、グローバル化、消費者意識の変化など、日本の経済社会の根幹での変化は、すべて小売業の姿や形に強い影響を及ぼしてきました。百貨店もその例外ではありません。
百貨店は変化への対応を続けるだけの存在ではありません。優れた百貨店はこれから起きると予想される変化を先読みして、新たな動き提示するような存在でなくてはなりません。これから起きることを先取りして、新しいライフスタイルや消費の姿を消費者に提案する存在でなくてはならないのです。それができない百貨店は、時代遅れの存在として見捨てられることになります。
本書は、「百貨店は技術革新のユーザーではなく、IT企業になるべき」「B2CからC2Bへの転換」「外商・お帳場が重要」などの新しい視点を提供する本格的流通論。日本経済の最新動向を押さえた筆者ならではのユニークな議論が展開されます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
えいなえいな
20
百貨店の社員という訳ではないですが20年近く携わっています。当然百貨店の未来には関心があります。長年携わっているだけあって書かれていることは現場でよく耳にする事ばかりで、自分もある意味では専門家なのか、と嬉しくなったりしました。一つ分からないのは文章の途中にいきなりコラムが差し込まれていて、どうしてこんな作りにしたのかよく分かりません。2019/04/01
hk
18
00年代はモータリゼーションの進展に後押しされ郊外化の時代だった。だが同時に製造業からサービス産業への移行が加速して都市部への人口集中が加速した。つまり足元の日本では郊外化と都市化という真逆の事象が同時進行しているのだ。郊外化によって輝くのは郊外型ショッピングモールである。そして都市化によって輝きを取り戻せるかもしれないのが百貨店だ。本書はこの百貨店の歴史背景と現状を点検しながら、IT時代における百貨店の渡世術を模索している。「電子レシート」「スマホ画像認証商品購買アプリ」など新機軸の紹介がためになった。2019/04/01
さやか
14
読みやすく分かりやすい。小売業の中で百年以上続いているのは確かに百貨店だけ。自社製造するメーカーには、差別化やコスト削減のメリットがあるが、時代の変化の対応に苦労する。百貨店は差別化は難しいが、変化への対応力はある。だから長年続く。経営者がその変化に迅速に的確に動けるかが重要だが。新たな視点だった。 あとITへの対応。昔からある企業がそれに適応していくのと、ITがある程度発展してからできた企業が適応していくのとでは全然意味が違うということ。勉強になった。2019/03/27
エリナ松岡
13
百貨店のお話ですが、さすが経済学者、少し広い視野で書かれていて良い内容でした。百貨店の事業を立て直すのは、1ヶ所直せばよい、とか、大鉈を振えばよい、というのではなく、あらゆる方面を少しずつ変化・調整させていくのが良いように思えるので、その意味では新機軸というものはなくとも多面的に百貨店の現状を分析し、その部分ごとにやるべきことを再確認する本書のスタンスは正しいのではないかと思います。2019/04/27
あつ子🐈⬛
12
「百貨店の現場で見られる興味深い事例がバレンタインデーにおけるチョコレートの販売である。名古屋駅の高島屋では、このイベントで22億円のチョコレートが売れたという(2017年)」 …毎年すごい人出ですもん。この催事に顔を出すためだけに来日する有名パティシエさんもいるそう。 きっと百貨店はまだ大丈夫。たとえ先がないと言われる異業種であっても、他にやれることはたくさんあるに違いない。 「群れの行動」「時間の経済学(予算制約と時間制約)」等これらキーワードを意識しながら、日々の仕事をこなしていこうと思います。2020/02/10
-

- 電子書籍
- 推しの実況者に、なぜか溺愛されています…
-

- 電子書籍
- capeta 新装版(7)
-
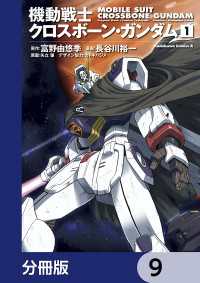
- 電子書籍
- 機動戦士クロスボーン・ガンダム【分冊版…
-
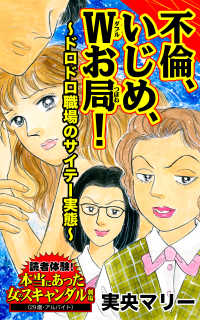
- 電子書籍
- 不倫、いじめ、Wお局!~ドロドロ職場の…
-
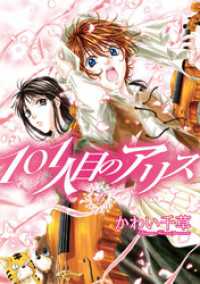
- 電子書籍
- 101人目のアリス(4) ウィングス・…




