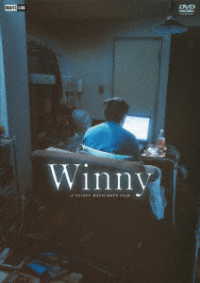- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
なぜ、金融バブルは繰り返されるのか。17世紀オランダで起きたチューリップバブルから、1929年の世界大恐慌、さらには1980年代末の日本のバブルに至るまで、古今東西で起きた「熱狂」とその崩壊過程を描く。バブルを希求する人間の本質と、資本主義経済の根幹に迫った名著がついに復活!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
wiki
20
訳語が生硬なのが玉に瑕に思う。概要を読み込むのに再読が必要だった。著者は陶酔的熱病(euphoria)に寄与する要因として「金融に関する記憶が極端に短い」事、「金と知性とが一見密接に結びついているかのようにおもわれている」事を挙げる。金融に関する記憶はもって四半世紀。手を替え品を替え投機は起こる。拝金教が金持ちこそ偉いとの誤認識を生み出し、熱狂させている。社会構造的に抑止出来ない事だ。懐疑的であれ、熱狂に参加するな、と賢人は書き遺した。転じて、今の世の中でも本書に記載の陶酔的熱病の典型は見出せる。良書。2019/05/15
一休
5
チューリップバブルからブラックマンデーまでバブルの様相を説明している。バブル(と崩壊)を語る本はいくつかあるが、本書は人間の特性から論じているのが興味深い。バブルの原因は、金融に関する記憶が極端に短い、金儲け=頭が良いという思い込みがあるとの指摘。またバブル崩壊後に損した市井の人々は儲けた人や買い煽った人を糾弾するが、実は前者も含めてバブルに乗った全ての人が悪い、そしてバブルはまた生まれるだろうというのはむしろ清々しい主張。バブルに乗せられないためには懐疑主義になり、渦中に入らないこととのこと。2025/04/13
Takao Terui
4
経済学者ガルブレイスによる、バブルについての長編エッセイ。投機の本質やそこに参入する人間の行動原理について、古今の歴史的事例を挙げつつ検討する。簡潔に、淡々となされる記述は、題材であるバブルに対する、ガルブレイスの醒めた距離感を示しており、思わずニヤリとしてしまう。「人間の群れ」の馬鹿さ加減が思い知らされ、世の中の違った面が見えてくる本作だが、エッセイという性格上、実際の数値・現象の詳述に踏み込まず、分量もコンパクトにまとまっている。 洗濯機を回している間に読み終わる、素晴らしい良書。 2014/10/25
ELW
3
南海泡沫事件の時の珍妙な会社群は知っていたが、本書で目にした出エジプトの際の紅海での落し物をサルベージする事業というのは、屈指の愚かさである。理性があれば投資しないし、設立もされないであろう。仮想通貨を教授が生きておられたらなんとおっしゃるか。2018/11/03
Mitz
3
バブルという陶酔的熱病の歴史と原理的な考察。17世紀のオランダにおけるチューリップバブルから、記憶に新しい日本のバブル崩壊まで、非常に分かりやすく、また興味深くまとめられている。著者曰く、熱病の原因は「金融に関する記憶は極度に短い」、「高騰・暴落の前に金融の天才がいる」の2点とのこと。なるほど、それは本書で紹介されている全ての事例に共通している。この本を読んで感じたのは、バブルの裏にある‘人間の存在’の大きさ。そして、バブルと熱狂的な流行や集団や国家の急速な右傾化・左傾化との共通点だ。面白かった。2013/03/03