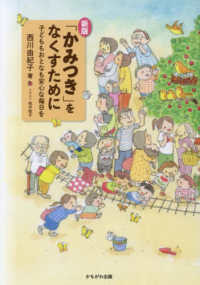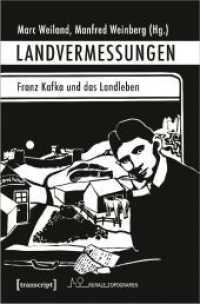内容説明
日本列島の旧石器時代はどこまでさかのぼれるのか? 縄文から弥生への移行の真相は? 遠くアフリカ大陸に誕生した人類が、どのようにしてここまでたどり着いたのか? 「わたしたちはどこから来たのか」をめぐる、明治から現在まで白熱し続ける大論争を、最新人類学の到達点から一望検証。いま、どこまでわかっているのか。残される謎は何か。日本人の最大にして不変の関心に、古人類学の第一人者が、深く、明快に解説します!
目次
第一章 太古の狩人たち――旧石器時代の日本列島人
第二章 人類の起源と進化
第三章 アジアへ、そして日本列島へ
第四章 日本人起源論――その論争史
第五章 縄文人から弥生人へ
第六章 倭国大乱から「日本」人の形成へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
60
まず最初に、岩宿遺跡の相沢忠洋、明石原人の直良信夫の業績を振り返っている。アマチュアとして本職の学者から冷遇される憂き目にあった二人だが、学問の世界が必ずしも、真実の前に公正ではなかった歴史は悲しい。人類の起源の謎解きも、現在はますます混迷の度を増しているようだ。それにしても縄文人のユニークさは際立っていて、常識的なイメージとは、かなり異なるらしい。弥生人との差異をうまく説明できれば、日本人の起源にかなり迫れるのだろうと思いながら後半を読んだ。今は新資料の出現を待ちたいところ。2019/03/05
樋口佳之
31
18年11月に文庫化されていて、かなりの加筆があったようです。参照されている研究時期が2010年代のものもあるので/都市では、通常なら比較的安全な少年~壮年期になっても死亡率があまり下がらず、要するにいつ死んでもおかしくない…江戸の住民の平均寿命は農村よりかなり短くなり…出生数よりも死亡数のほうが上回ってしまって、その人口減少分を恒常的に近郊農村から吸収し…その一方でまた、そうして引き寄せた奉公人や出稼ぎ人をばたばたと早死にさせる、という構図に…まさに蟻地獄/テーマに外れてますがここが一番印象的でした2019/03/30
HMax
23
小さな文字で「人類誕生から縄文・弥生へ」とある通り、いつ類人猿と別れたのか?デニソワ人の話しとか、結構な部分を人類誕生に割いています。「骨が語る日本人の歴史」の方が面白かったが、こちらの方が数年新しい情報がありました。結論はやはり、あっちこっちから来て日本列島で生まれた。それにしても縄文前期(6500-6000年前)は今よりも年平均2度ほど高かったそうで、びっくり。2019/08/10
南北
20
日本列島の旧石器時代はどこまで遡ることができるのか、また日本人はどこから来たのかについて概観した本です。旧石器時代については2000年に発覚した捏造事件で振り出しに戻ってしまい、今後の研究が待たれるところです。また、日本人の起源については、遺伝的な多様性や重層性を矛盾なく説明できる統一モデルはできていないようです。また、弥生時代も2003年に紀元前10世紀に遡る見解が出され、人骨から見ると急激に渡来系が増加しているのに、土器は縄文系が多い時代が続いているなど、こちらも今後の研究が待たれるところです。2019/05/24
わたなべよしお
19
日本人、日本列島をめぐる人類史が最近の知見も含めて外観できる。公平な見地に立っているようだし、入門編、あるいは素人が読むには優れた教科書となるのではないか。それだけに迫力や面白さにはやや欠けるが、致し方ないだろう。2019/03/10
-
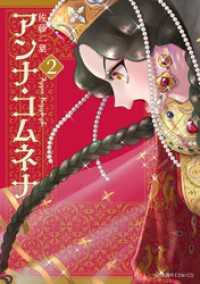
- 電子書籍
- アンナ・コムネナ(2)