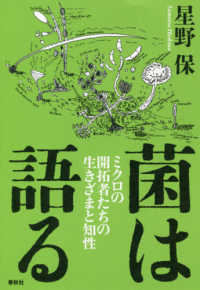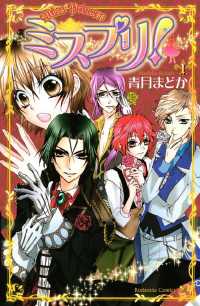内容説明
「路地(同和地区、被差別部落)って何?」「住所による差別なんて今もあるの?」「知らなければ差別はなくなる?」「同和教育、同和利権とは?」全国千か所以上の路地を歩いた著者が全ての疑問に答えます。差別について、他者について、イチから考えてみよう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たくろうそっくりおじさん・寺
41
『日本の路地を旅する』や『異形の日本人』『被差別の食卓』のルポライター・上原善広が、部落差別の現状と歴史・差別論をわかりやすく一冊に。わかりやすいだけでなく面白かった。差別される側だけではなく、差別する側の事も考察していて、リベラルで公平な視点が身につきそうだ。部落差別って、まだ終わっていない江戸時代なんだよなぁ…。みんなで早く終わらせたいものだ。左翼系や解放系の出版社ではなく、筑摩書房の少年向け新書でこういう本が出るようになった事は素晴らしいと思う。理解は難しくても「気づき」ならばできる。2014/06/01
きいち
35
これは人に薦めたくなる一冊。◇部落差別の過去と現在を非常にプレーンに説くだけでなく、それを通じて、「知ること」の価値を実感させてくれる、とても元気になれる本だ。◇「差別はなくならない」ことを前提にすること。人間、差別して当然、それは病気のようなものなの。でもこの時点で善悪を言ってしまうと思考が止まってしまうから(内藤朝雄さんの『いじめ』論が思い出される)、このことを前提に改善を考えよう、と。その武器となるのが、「知ること」であり、「他者への気づき」だと。◇そうして、「路地」を知ることが、大切な教養となる。2014/04/21
けんとまん1007
30
おそらく、自分はここで書かれている「一般の人」に入るのだろうと思う。何か、差別を受けたという印象はない。と言うか、自分の周囲を考えても、思い当たることがない。もちろん、気づいていないだけかもしれない。社会の教科書等ででききた言葉の意味を初めて知った。確かに、地域による違いという印象はある。それよりも、目からうろこだったのは「差別するから人なんだ」という視点。その上で、どう対応するのかが大切であるという視点だ。2015/03/21
kinkin
28
筆者は同和地区や被差別部落のことを「路地」と書いている。これは、作家の中上健次が初めて使ったということを知った。この「路地」について「全く知らない」という人から、その存在を「知ってるけどよくわからない」という人を中心に書いており、筆者の考えや体験を読み手に考えさせている。2014/01/27
gtn
26
人は差別する生き物との前提に立ち、そのうえで差別に対して抗え、もがけと著者は訴える。もがかなければ、易きに流れ、何も変わらない。同和問題の取り組みも、もがきの積み重ねといえる。どんな小さな差別も糾弾する、部落史を学ぶ程度にして時が解決するのを待つ、金持ちになるという各団体の主張について、著者はいずれも正しいという。どの主張も、もがいた末に見いだしたものであり、正解は一つではないということだろう。2018/11/24