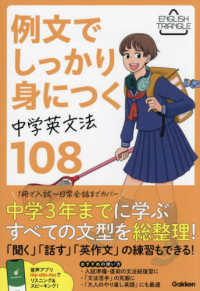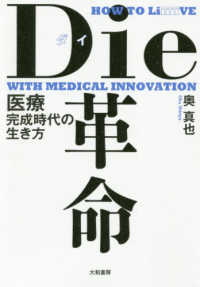内容説明
知っているようで知らない「み仏の常識」てんこもり!お釈迦さまの一生から、仏像の楽しみ方、お焼香の回数まで完全網羅。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yk
5
日本における宗教観がわかりやすく書かれていた。宗教ってやっぱり人が作ってるんだなって思いました。たくさんのストーリーがあっておもしろい。仏様って考え方も好きです。弥勒菩薩の半跏趺坐の理由もわかってよかった。たくさんの人に読んでほしい本です。2018/07/29
オリバー
3
入門入門。鑑真氏へ感謝(5年振り4度目)2013/11/26
田山河雄
2
キリスト教には誰もが手に出来る聖書があるのに、仏教には何故無いのだろうか。キリスト教はまず神様がいて世界を創造した(エホバ他はユダヤ民族の守り神で、キリストは神の子)と云うのに、仏教のお釈迦様は全知全能の神様では無い(修行して真理を知った人、悟りを開いた人)らしい。この違いは考えてみると際立つようだ。宗教とは何とも…と云っては不謹慎すぎるが、聖書を読んでみるのもアリかと思う。そう言えば昨日「エデンの東」を何十年ぶりかでTVで見た。恥ずかしいが目頭を熱くして拝見した。2021/05/12
ぞるば
2
読みやすかったです。もう何回入門したかわからん。はやく入門を卒業したい。最後のコラム7の佐々井秀嶺師というかたのことは初めて知りました。2019/02/10
たろーたん
1
神社と寺院、神と仏の関係だが、聖徳太子以降、国家プロジェクトとして各地に国分寺、国分尼寺が建てられ、中央集権国家が出来上がっていく過程で、日本固有の神々は仏法を守る役割を担うとみなされるようになった。平安時代になると、神と仏の関係は「本地垂迹」という考えで表されるようになり、神道の神様たちは、仏や菩薩が私たちを救うための仮の神様の姿と見做されるようになった。こうして、仏や菩薩が神社にも祀られるようになり、神仏習合となった。だが、明治時代に神道を国教とするため、神社と寺院を切り離す神仏分離が行われる。(続)2023/12/21