内容説明
オハイオ州の架空の町ワインズバーグ。そこは発展から取り残された寂しき人々が暮らすうらぶれた町。地元紙の若き記者ジョージ・ウィラードのもとには、住人の奇妙な噂話が次々と寄せられる。僕はこのままこの町にいていいのだろうか……。両大戦に翻弄された「失われた世代」の登場を先取りし、トウェイン的土着文学から脱却、ヘミングウェイらモダニズム文学への道を拓いた先駆的傑作。(解説・川本三郎)
-

- 電子書籍
- 仲良しチーム、成果主義では会社が壊れる…
-

- 電子書籍
- きれいになりたい!【分冊】 12巻 ハ…
-
![[ハレム]どっちにしろ、どつぼ 第3話 ハレム](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1128522.jpg)
- 電子書籍
- [ハレム]どっちにしろ、どつぼ 第3話…
-

- 電子書籍
- シンデレラになった家政婦【分冊】 2巻…
-
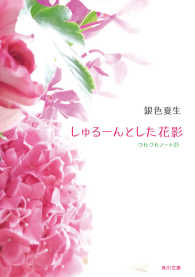
- 電子書籍
- しゅるーんとした花影 つれづれノート(…



