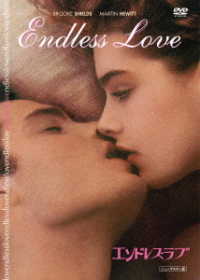内容説明
ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが生前に公刊した著書は、たった2冊である。1冊は『論理哲学論考』(1922年)。この書をもって、哲学のすべての問題は解決されたと確信したヴィトゲンシュタインは、哲学から離れ、小学校の教師に転身を遂げる。教師として暮らす中でその必要を感じ、みずから執筆したのが、残る1冊である本書(1926年)にほかならない。本書は、その本邦初訳となる記念碑的訳業である。
目次
小学生のための正書法辞典
序 文
本 文
解 説(丘沢静也)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
96
哲学者のヴィトゲンシュタインが刊行したドイツの小学生向け辞典です。彼はこの本と有名な「論理哲学論考」だけを刊行していたようです。彼の前文と解説が参考になりますが、私はこの本を、昔のいわゆる豆単のような感じで利用しています。自分のしている言葉をチェックする方法で行っています。単語の説明も1行くらいしかないので。2023/12/03
Ex libris 毒餃子
7
ヴィトゲンシュタイン研究家が読んどけば良いと思った。かなりきつかったです。2019/02/24
Susumu Kobayashi
5
原題は『小学生のための辞典』で、内容もまさに辞典、というか単語集なのであった。読みどころは、どんな単語をヴィトゲンシュタインが選び、どのように配列したかということだろう。これで小学生レヴェルのドイツ語単語を習得しようとおもったが、もくろみははずれてしまった。除去(die Abnahme)とか、同業組合(die Innung)とか、上司(der Vorgesetzte)とか、小学生が知っているべき単語なのだろうかとも思った。単語を覚えるには、この本はあまり役に立たない。2018/12/29
takao
2
ドイツ語のスペリング2022/10/06
YOa suie
1
言語に二重分節性があるように辞書にも入れ子構造があると思った。ウィトゲンシュタインは収録語の選定以上に配列を工夫したという。今まで辞書や単語帳の配列を気にしたことが無かった。3000語が収録されているなら語数のみが重要で配列には意識が向かなかった。しかし良く考えれば逆引き辞典など配列が変わることで異なる機能を持たせている。ページというのも構造だと思う。100ページに3000語なら30×100という構造を持っていると考えられる。電子辞書はその構造を持たないか3000×1という単位だと考えることも出来る。