- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
筆者が上方落語の魅力に溺れた1970年代、その中心は俗に「四天王」と呼ばれる六代目笑福亭松鶴、桂米朝、三代目桂春團治、桂小文枝(後の五代目文枝)の四人の師匠連であった。最後のお一人となった春團治師も2016年1月9日に85歳で亡くなり、ひとつの時代が終わった感がある。本書では38の演題を厳選、懐かしい師匠たちの舞台裏噺から芸の魅力、人の魅力、お囃子さんまで、40年の思い出を語り尽くす。番外として、タモリが吉原で発見し、鶴瓶が演じ、歌舞伎になった新作落語『山名屋浦里』の裏話をお楽しみください。
目次
第1章 上方らくご精選38席 青空散髪・網船・有馬小便・いかけや・浮かれの屑より・おごろもち盗人・お玉牛・鬼あざみ・貝野村・掛取り・軽業・近日息子・蔵丁稚・稽古屋・滑稽清水・皿屋敷・質屋芝居・死ぬなら今・昭和任侠伝・善光寺骨寄せ・高尾・蛸芝居・田楽喰い・天王寺詣り・電話の散財・野崎詣り・初天神・ふぐ鍋・堀川・豆屋・みかんや・深山隠れ・大和閑所・遊山船・夢八・弱法師・ろくろ首・山名屋浦里/第2章 お囃子さん列伝/第3章 音と映像と文字と/「あとがき」という題の言い訳
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遊々亭おさる
13
上方落語の低迷期を支えた四天王をはじめ、演芸場で庶民に笑いを提供してくれた今は亡き噺家さんたちの芸の魅力と思い出話を三十八の演目に織り混ぜて語られる一冊。演者が変われば噺の風味が変わる。何度同じ噺を聞いても飽きることなき古典落語の謎が明かされます。上方落語の魅力のひとつには「あんたもアホなら、わたいもアホだ。同じアホ同士仲良くしまひょ」の精神があるのではないかと著者が推察するアホ・バカ論を読んで思う。自己責任やなんやらとギスギスした現代社会。令和の世は、アホ同士、笑って生きていける世の中でありますように。2019/05/01
浅香山三郎
12
小佐田さんのちくま新書のシリーズ3冊目。かなり珍しい演目(?)も含む38席を取り上げ、演者それぞれの演じ方、エピソードを濃厚に解説。音源、速記の情報も明示してあるのがありがたい。上方四天王とその弟子たちの魅力や、話の背景解説なども丁寧で、上方落語の演目について、もつと知りたいといふ時の入り口にもなる。上方の社会全般の理解にも、落語を聴くことは繋がつてゐるのがよくわかる。2019/06/10
捨拾(すてろう)
6
上方落語のレジェンドの方々が、次々と鬼籍に入られているので、当時を現場で知る小佐田氏の記述は実に貴重であり、そして何より演芸に対する愛に溢れている文章に、温かい気持ちになる。桂吉朝さんの最後の舞台となってしまった弱法師、楽屋でのやりとりに涙が出た。2020/12/14
やまねっと
5
僕は上方に住んでるけど、江戸ばなしが、好きなのだが、上方落語も奥が深くて面白い噺が多いのだと思った。上方落語の話だけではなくてお囃子さんのことも取り扱っており、興味深く読んだ。 僕はこの作家を米朝一門の作家だと思っているので、米朝一門の話はやはり豊富で面白い。 舞台裏話はこれで完結編だが、これに載らなかったこぼれ話なんかも今後披露していただきたい。2019/03/14
今Chan
4
前作2作に比べると、枝雀の登場が少ないのが仕方ないとは言え、枝雀ファンとしては物足りない気もしたけれど、でもさすが小佐田先生。感動の舞台裏を綴ってくれている。 枝雀のオーバーアクションに三代目染丸師の影響があったのでは。という推測や、江戸の「与太郎」は創り出されたバカだが上方の「イチビリ」は仲間としてのアホかも。という「理論」は、新鮮に思えた。枝雀落語にカーテンコールをしたかった。2019/01/24
-

- 電子書籍
- 婚約破棄だ、発情聖女。(コミック)【単…
-
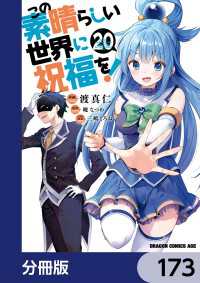
- 電子書籍
- この素晴らしい世界に祝福を!【分冊版】…







