内容説明
ハーバード大学客員教授として一年間,ライシャワー日本研究所に滞在した著者が,この社会を中心近くの崖っぷちから観察した記録.非日常が日常化した異様な政権下,この国が抱える深い暗部とそれに対抗する人々の動きをリアルタイムで追う.黄昏の「アメリカの世紀」とその未来について考察する,『世界』好評連載の書籍化.
目次
目 次
はじめに トランプのアメリカに住む 2017─18
第1章 ポスト真実の地政学──ロシア疑惑と虚構のメディア
第2章 星条旗とスポーツの間──nfl選手の抵抗
第3章 ハーバードで教える──東大が追いつけない理由
第4章 性と銃のトライアングル──ワインスタイン効果とは何か
第5章 反転したアメリカンドリーム──労働者階級文化のゆくえ
第6章 アメリカの鏡・北朝鮮──核とソフトパワー
終 章 naftaのメキシコに住む──1993─94
あとがき──キューバから眺める
主な引用・参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
101
アメリカの中間選挙後にこの本を読む。どんどん、アメリカに倣っていうような世界に対し、その中心であるアメリアでは何が起こっているのかを記しています。アメリカン・ドリームの幻想が却って人々の首を絞めているように思えていたので「ラストベルト」に言及した章は、まさに現実となった『泳ぐひと』のような恐ろしさがある。そして星条旗と国歌に対し、アメリカの成り立ちの血腥さと欺瞞の対比、アメリカの男性達が求められる「男性さ」を演じるために何をしてきたのかも重い。しかもそれは今となっては決して対岸の火事でもないのだ。2018/11/20
k5
76
吉見先生が一年間ハーバード大学で教えた経験から書かれた本で、『平成時代』などと比べるとコラム的ですが、当方がアメリカについて無知なこともあり面白いです。星条旗の象徴するアイデンティティや、MeTooで暴き出されたマッチョイズムなど、深掘りしたいテーマ満載。全米ライフル協会が主要企業の提供する特典(配送料のディスカウントなど)を元に会員を増やして発言力を増しているのに対し、SNSでボイコットをするというくだりを読んで、BLMをはじめとするかの国の運動について、分かったような気になりました。2020/08/14
佐島楓
76
トランプのことを考えると際限なく腹が立ってくるので、アメリカの大学システムについて。アメリカの大学のカリキュラムは、履修する講義が日本の半分ほどでよく、その代わり週二回フィードバックや細かいフォローがあるようだ。日本の大学で今勉強する私にはうらやましい話。深める前に課題に追われ、終わったら忘却するサイクル。教員側と学生側の負担は増えるが、学びの質でいえばアメリカ式のほうが断然いい。考える姿勢になれないまま時間ばかり過ぎるのは、学生にとってもったいない。2018/10/06
rico
42
存在そのものが悪い冗談のような大統領が誕生してはや2年が経つ。すぐクビになるかと思ったが、なかなかしぶとい。著者は1年間のアメリカ滞在での経験を軸に、今アメリカで起こっていることに鋭く切り込んでいく。#Me Tooのムーブメント、白人非エリート層の鬱屈、色あせたアメリカンドリーム。確かに、アメリカは世界のリーダーであることをやめ、普通の国になろうとしている。さて、アメリカにどっぷり依存している日本はどうするのか。好著。2018/10/25
skunk_c
42
東大の社会学の先生が1年間ハーバードで客員していたときに書いたもので、雑誌『世界』に連載されていたものをまとめたものだそうだ。基本アンチ・トランプ(さらにアンチ共和党)の姿勢で、トランプは嘘つきと切って捨てながらも、そのトランプが支持され、頂点に立ったアメリカを様々な角度から観察している。また、ハーバードのシステムについても高評価しながらその内容を上手く伝えている。金正恩との交渉などアップ・トゥ・デートな内容もあり、また日本についても言及するなど、多角的で読み応えがあった。ただややインテリ臭が鼻につくが。2018/09/30
-

- 電子書籍
- ぼっちの僕に強制彼女がやってきた【単話…
-
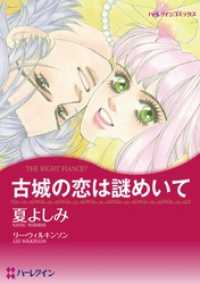
- 電子書籍
- 古城の恋は謎めいて【分冊】 2巻 ハー…
-
![【花とゆめプチ】[カラー版]兄友 第7話 花とゆめコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0531315.jpg)
- 電子書籍
- 【花とゆめプチ】[カラー版]兄友 第7…
-
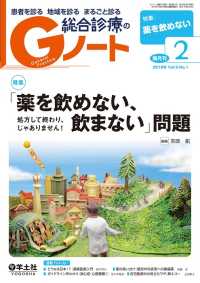
- 電子書籍
- 「薬を飲めない、飲まない」問題 - 処…
-
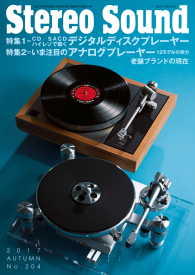
- 電子書籍
- 季刊ステレオサウンド No.204




