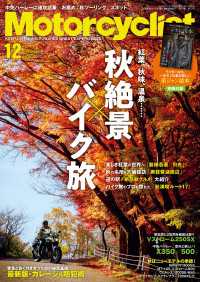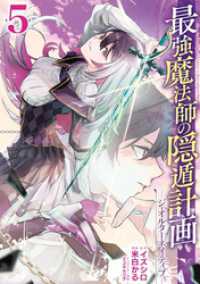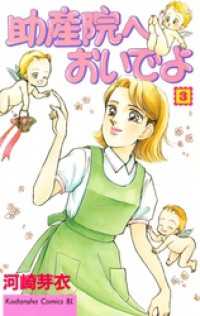- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
本気で変えたい覚悟のある経営者に捧ぐ。
企業変革(チェンジ・マネジメント)は、経営者に求められる根本的な仕事であり、このために経営者が存在するといってもよい。著者は、マッキンゼー出身で20年にわたり、多様な業界で次世代成長戦略、全社構造改革のプロジェクトにかかわってきた。現在は、ビジネススクールで教鞭をとりつつ、ファーストリテイリングや日本電産をはじめ、日本を代表する各企業のアドバイザーや、30を超える企業での次世代経営者育成にかかわっている。本書では、著者による数多くの変革の経験を踏まえ、内外企業の事例を挙げながら、変革の方法を説いた、著者の仕事の集大成ともいえる一冊。今、なぜ変革なのか(Why)、という意識作りに始まり、企業変革の代表的モデルの解説(What)、変革へのアプローチ(How)、そして、変革者(チェンジリリーダー)になるための条件(Who)を説いていく。V字回復やカリスマ依存ではない、企業の体質改善と、持続的な成長エンジンを組み込むことが最終目標である。
目次
はじめに
序章 なぜ今、成長なのか?(Why)
第1部 変革の4モデル(What)
第1章 シュリンク・トゥ・グロー(V字回復)モデル
第2章 セルフ・ディスラプション(自己破壊)モデル
第3章 ポートフォリオ・オブ・イニシアティブ(組合せ)モデル
第4章 メビウス(永久反転)運動モデル
第5章 どのモデルを選ぶべきか?
第2部 変革のプロセス(How)
第6章 変革を仕掛ける
第7章 変革の青写真を描く
第8章 変革を実践する
第9章 変革を継承する
第3部 変革者(チェンジリーダー)の条件(Who)
第10章 経営の変革者
第11章 変革リーダーをめざせ
おわりに
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
koji
tkokon
Great Eagle
hide