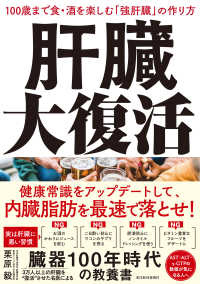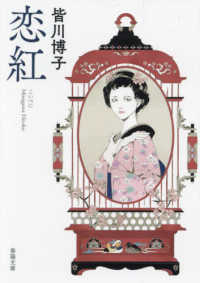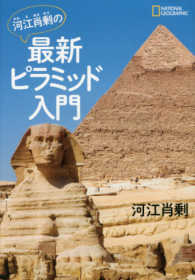- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
「非認知能力」は、2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・J・ヘックマン博士によって世界で初めて提唱されました。
例えば、コミュニケーション能力や思いやり・共感性、忍耐力・自制心、意欲・向上心などといった、テストでは数値化が難しい幅広い力や姿勢を含み、学歴や仕事など将来の成功の支えとなるものとして、今、世界的に注目されています。
子どもにとっても、大人にとっても必要とされる非認知能力は、どうやって身に付けていけばよいのでしょうか?
そもそも、この非認知能力とはどのような力なのでしょうか? なぜ、今、これほどまでに注目を集めているのでしょうか?
これらの問いに理論と実際を交えてわかりやすく答えるとともに、産官学民ですでに始まっている大人たちの挑戦についても紹介しています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムーミン
28
読み直し。やっぱり本校の研究の方向に大きく重なります。中山先生に直接ご指導いただく機会を作ります。2020/01/22
ムーミン
23
最近たくさん出ている「非認知能力」に関する本と内容的には同じでした。「見える学力と見えない学力」と言っていたずいぶん以前からの問題意識が、ここにきてどうしても避けて通れない、立ち行かなくなってきているのを強く感じます。2019/06/28
ムーミン
22
さらに読み直し。読み返すほど自分の中に落ちていく部分と、新たな疑問というか、もっと深いところを知りたいと思う部分が出てきます。やっぱり直接伺ってみたいです。子どもたち、私たちの未来のために。2020/01/26
kei
15
世界的に、コミュニケーション能力や思いやり・共感性、忍耐力・自制心、意欲・向上心などといった「非認知能力」が注目されており、この非認知能力を伸ばすには体験を内面化し、経験を振り返ることにより学んで、能力を獲得・向上させる、ということでした。2019/08/03
nagata
9
外からある基準(物差し)を設けて数値化した能力を比較評価するのがこれまでの教育のあたりまえ。これに対して、そもそも自らが外の世界や人々とどうかかっていくのかをとらえ、伸ばそうとするには、周りの大人が教える立場から相手(それが大人であれ子どもであれ)と同じ主体的なかかわりに代わっていくことが大切と読めた。読んで理解するよりも、実践的に動いてみて振り返りつつ再読するものかも。2025/02/28