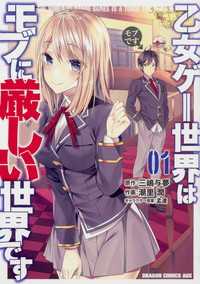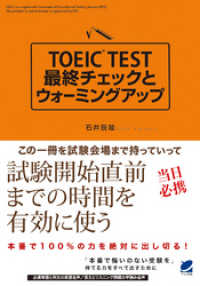内容説明
「原発を止めてほしい」――そう願う住民らにとって「最後の砦」は裁判所だった。しかし結果は連戦連敗。なぜ司法は国策に沿う判決を下してきたのか。これまでマスコミとの接触を避けてきた元裁判官たちが明かす原発訴訟の真実。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
35
3.11で「原発神話」は崩壊した。それを支えていたのは、行政府、電力会社、マスコミ、そして裁判官もだった。本著の白眉は原発訴訟に関わって判決を書いた元裁判官が実名・顔出しで登場している点にある。読んで感じたのは、所詮、裁判官も人の子だなあということ。人事も気になれば、ときの世論の影響を受ける。基本文系だから、科学用語の理解に難儀もする笑。でも、やはり司法の独立という矜持だけは失ってほしくない。唯一の希望は、少しずつ若手の裁判官の意識が変わってきたという点か。2019/03/16
RED FOX
9
裁判官のバッジのモチーフは八咫鏡!原発に関する主な裁判についての検証。まあ長-いあいだ原告(住民たち)側の連戦連敗なのですが、そんな中でも徐々に国・電力会社側に牙をむいた判決が出てくる、最高裁で負けるが。そして3.11以降の裁判官達の新たな動きのルポ。憲法76条3「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」の復活の兆し。帯の「高村薫さん絶賛!」で迷わず買ったが(ブクオフだが)読んで良かった。行政と国民、どちらも大変大事だからこそ司法は頑張ってください。2016/05/20
ERNESTO
3
柏崎刈羽1号機訴訟の1審・新潟地裁で原告敗訴の判決を出した、西野喜一元判事の「判決を左右する要素」が全てと言って良いだろう。 曰く、訴訟法が国策を争うようにできていない、 国賠や公害訴訟など行政権力が関心を持ちそうな事件の全てとも言え、最高裁に別途報告することになっている「報告事件」の国敗訴でない判決を書けとの無言の心理的プレッシャー、 自分の良心を貫いた判決を書いても上級審で破棄されれば、当事者に時間と労力を消費させただけとの徒労感、 2013/05/31
Mao
2
『少数派の声に耳を傾けるのが司法の役割だ。小さな声のなかにも取り上げるべき真実があれば、国策といえどもひるむことなく「間違っている」と判決することが裁判所にはできる。それによって多数派の暴走に歯止めをかけることが、裁判所の存在意義のはずだ。』 一日も早い実現を望みます2013/07/30
dante
1
原発の仕組みがわからなくても読みやすくなっている。2015/02/06