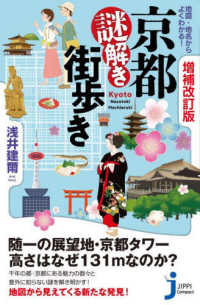内容説明
ここは沼津市のデイサービス施設「すまいるほーむ」。デイルームや入浴介助の場で、ふと語られる記憶の数々。意外な戦争体験、昭和の恋バナ、心に沁みるエピソード。多彩な物語が笑いと涙を呼び、豊かな時間が流れる。聞き書きや思い出の味の再現、人生すごろくなどユニークな取り組みが問いかける、老いることの価値とは。深い気づきと新鮮な感動に満ちた一冊。『介護民俗学へようこそ!』改題。(解説・伊原和人)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
40
「老い」が「成熟」として尊重される世界に。これは先達にとってだけでなく、これから老いる全ての我々のためにも実現したい世界観。◉その手法として介護民俗学の創造・実践を紹介。これは介護する側にも、地域社会にも敷衍できる方法論であると。だから、希望。◉「50歳を過ぎて尊敬されない人生は虚しい」とか村上龍は言ったが(それはそれで重要だろうが)、「どの人もホント興味深いよね」と言いあえる心象はさらに重要だろう。その確度をあげるために「聞き書き」は今後のキーワードと思っていたところだったので、その意を強くしました。2018/08/14
アナクマ
23
実践と検証という2軸で再読開始。◉1章_聞き書きの〈沃野〉へ。介護する側とされる側という固定・硬直化された役割を壊して逆転させる力「介護の有り様を柔軟な開かれたものに変えていく可能性」が、聞き書きにはあるという。例えば「手のかかる存在でしかなかった認知症の利用者さんが…尊敬すべき人生の大先輩…人として愛おしくなったのである」◉繰り返し参照したい重要な二行は「民俗学の主たる方法である聞き書きが、介護現場でも有用性を持つのではないか」と「語り手と聞き手の関係性」。とくに前段3語の意味と関係性に注目。2023/03/22
浅香山三郎
13
著者は民俗学者で大学教員だつたが、介護の現場へ。介護施設の利用者と運営者の固定的な考へ方を捉へ直し、利用者の人生を聞き書きすることで、介護施設の新しいあり方を模索してゆく。利用者のお年寄りの食や恋愛、生業、障害などを聞き書きにより深く理解することで、介護をうける中でのよりよい生き方が模索される。 聞き書きの中身の興味深さと、介護するといふあり方の可能性を問ふ多義的な試みの書である。2025/01/24
A.Sakurai
6
前著「驚きの介護民俗学」は介護の場に民俗学を導入して効果を上げる,すごい内容だったのだが,厳しい介護現場で展開できるのか疑念はあった.本書はまさにその回答編として,小規模な介護施設に移って実践した記録となる.聞き書きの事例自体は前著の方が豊富だが,本書では聞き書きが介護するものと介護されるものという一方的な関係を崩すことで現場に良い影響が生まれる事例が中心となる.認知症の方が語る物語に遠野物語のような異世界を覗く面白さや,聞き書きが「聞く」より「書く」創作の楽しさに依拠しているなど,ハッとする指摘も多い.2018/06/06
まゆ
3
聞き書きという方法を介護現場で実践するノンフィクション。介護する側、される側という関係でなく、利用者の方にスタッフが踊りを教えてもらい先生と生徒みたいになったりそんな人と人という普通の関係ができているところが素敵だと思った。聞き書きをされる人の人生をみんなで振り返って共感してよりその人のことを深く知ることで理解し合える居心地の良い場所になっているすまいるホームのような介護施設が増えるといいなと思った。利用者、スタッフみんなで作っていく自分たちの場所というのが印象的だった。2018/09/23
-
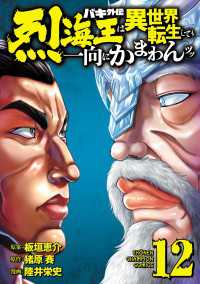
- 電子書籍
- バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向…
-

- 電子書籍
- TRONWARE VOL.201 (T…
-
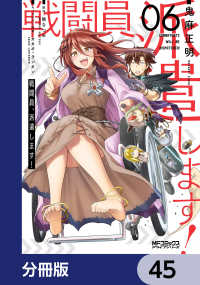
- 電子書籍
- 戦闘員、派遣します!【分冊版】 45 …
-
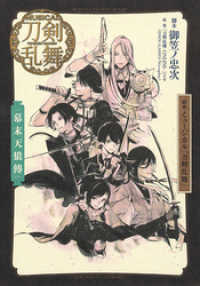
- 電子書籍
- 戯曲 ミュージカル『刀剣乱舞』幕末天狼…