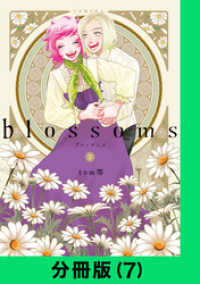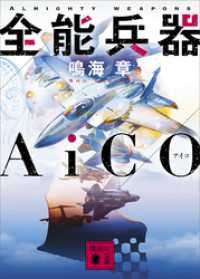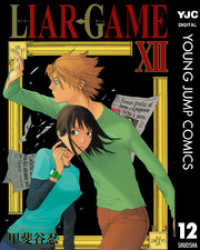内容説明
「人よく菜根を咬みえば,則ち百事なすべし」.菜根は堅くて筋が多い,これをかみしめてこそものの真の味わいがわかる.明代末期に三教(儒仏道)兼修の士洪自誠が自身の人生体験を基にかみしめて味わうべき人生の哲理を簡潔な語録の形に著わした.本文庫版には注に解説に校注者の研究水準の高さが充分に盛り込まれている.
目次
目 次
凡 例
菜根譚題詞
菜根譚前集
一、道徳に棲守する者は
二、世を渉ること浅ければ
三、君子の心事は
四、勢利紛華は
五、耳中、常に耳に逆うの言を
六、疾風怒雨には
七、じょう肥辛甘は真味にあらず
八、天地は寂然として動かずして
九、夜深く人静まれるとき
一〇、恩裡に由来害を生ず
一一、藜口けん腸の者は
一二、面前の田地は
一三、径路の窄き処は
一四、人と作りて甚の高遠の事業
一五、友に交るには
一六、寵利は人前に居ることなかれ
一七、世に処するに一歩を譲るを
一八、世を蓋うの功労も
一九、完名美節は
二〇、事々、個の有余不尽の意思を
二一、家庭に個の真仏あり
二二、動を好む者は、雲電風燈
二三、人の悪を攻むるは
二四、糞虫は至穢なるも
二五、矜高倨傲は
二六、飽後に味を思えば
二七、軒冕の中に居りては
二八、世に処しては
二九、憂勤は是れ美徳なり
三〇、事窮まり勢蹙まるの人は
三一、富貴の家は
三二、卑きに居りて後
三三、功名富貴の心を
三四、利欲は未だ尽くは心を
三五、人情は反復し
三六、小人を待つは
三七、寧ろ渾がくを守って
三八、魔を降す者は、先ず自心を降せ
三九、弟子を教うるは
四〇、欲路上のことは
四一、念頭の濃やかなる者は
四二、彼は富もてせば我は仁
四三、身を立つるに一歩を高くして
四四、学ぶ者は、精神を収拾し
四五、人々に個の大慈悲あり
四六、徳に進み道を修むるには
四七、吉人は作用の安祥なるを
四八、肝、病を受くれば
四九、福は事少なきより
五〇、治世に処しては
五一、我、人に功あらば
五二、恩を施す者は
五三、人の際遇は
五四、心地乾浄にして
五五、奢る者は富みて而も足らず
五六、書を読みて聖賢を見ざれば
五七、人心に一部の真文章あれども
五八、苦心の中に
五九、富貴名誉の、道徳より来たる
六〇、春至り時和らげば
六一、学ぶ者は段の兢業的の心思あり
六二、真廉は廉名なし
六三、欹器は満つるを以て覆り
六四、名根の未だ抜けざる者は
六五、心体光明なれば
六六、人は名位の楽しみたるを
六七、悪を為して人の知らんことを
六八、天の機緘は測られず
六九、燥性の者は火のごとく熾んに
七〇、福は徼むべからず
七一、十の語九中るも
七二、天地の気は暖なれば則ち生じ
七三、天理の路上は甚だ寛く
七四、一苦一楽、相磨練し
七五、心は虚にせざるべからず
七六、地の穢れたるものは
七七、泛駕の馬も、駆馳に就くべく
七八、人は只だ一念貪私なれば
七九、耳目見聞は外賊たり
八〇、未だ就らざるの功を図るは
八一、気象は高曠を要して
八二、風、疎竹に来たる
八三、清にしてよく容るることあり
八四、貧家も浄く地を払い
八五、かん中に放過せざれば
八六、念頭起こる処
八七、静中の念慮澄徹なれば
八八、静中の静は真静にあらず
八九、己を舎てては
九〇、天、我に薄くするに
九一、貞士は福を徼むるに心なし
九二、声妓も晩景に良に従えば
九三、平民も肯て徳を種え
九四、祖宗の徳沢を問わば
九五、君子にして善を詐るは
九六、家人、過あらば
九七、此の心常に看得て円満ならば
九八、澹泊の士は
九九、逆境の中に居らば
一〇〇、富貴の叢中に生長する的は
一〇一、人心、一たび真なれば
一〇二、文章は極処に做し到れば
一〇三、幻迹を以て言えば
一〇四、爽口の味は
一〇五、人の小過を責めず
一〇六、士君子、身を持するは
一〇七、天地には万古あるも
一〇八、怨は徳に因りて彰わる
一〇九、老来の疾病は
一一〇、私恩を市るは
一一一、公平正論には
一一二、意を曲げて人をして喜ばしむる
一一三、父兄骨肉の変に処しては
一一四、小処に滲漏せず
一一五、千金も一時の歓を結び難く
一一六、巧を拙に蔵し
一一七、衰颯の景象は
一一八、奇に驚き異を喜ぶ者は
一一九、怒火慾水の正に騰沸する
一二〇、偏信して奸の欺くところと
一二一、人の短処は
一二二、沈々不語の士に遇わば
一二三、念頭昏散の処は
一二四、霽日青天も、たちまち変じて
一二五、私に勝ち欲を制するの功は
一二六、人の詐を覚るも
一二七、横逆困窮は
一二八、吾が身は一小天地なり
一二九、人を害するの心は
一三〇、群疑に因りて独見を阻む
一三一、善人、未だ急に親しむこと
一三二、青天白日的の節義は
一三三、父は慈に子は孝に
一三四、妍あれば、必ず醜ありて
一三五、炎涼の態は
一三六、功過は少しも混ず容からず
一三七、爵位は宜しく
一三八、悪は陰を忌み
一三九、徳は才の主にして
一四〇、奸を鋤き倖を杜ぐは
一四一、当に人と過を同じくすべく
一四二、士君子は貧にして
一四三、饑うれば則ち附き
一四四、徳は量に随って進み
一四五、一燈螢然として
一四六、己を反みる者は
一四七、事業文章は
一四八、魚網の設くる
一四九、人と作るに
一五〇、水は波だたざれば
一五一、一念にして鬼神の禁を犯し
一五二、事はこれを急にして
一五三、節義は青雲に傲り
一五四、事を謝するは
一五五、市人に交わるは
一五六、徳は事業の基なり
一五七、前人云う、<ookagib/>自家の無尽蔵を
一五八、道は是れ一重の公衆の物事なり
一五九、人を信ずる者は
一六〇、念頭の寛厚なる的は
一六一、善を為して其の益を見ざるも
一六二、故旧の交わりに遇いては
一六三、勤は徳義に敏し
一六四、意の興るに憑りて
一六五、人の過誤は
一六六、能く俗を脱すれば
一六七、恩は宜しく淡よりして
一六八、心虚なれば則ち性現わる
一六九、我貴くして人これを奉ずるは
一七〇、<ookagib/>鼠の為に常に飯を留め
一七一、心体は便ち是れ天体なり
一七二、事なきの時は
一七三、事を議する者は
一七四、士君子、権門要路に処れば
一七五、節義を標する者は
一七六、欺詐的の人に遇わば
一七七、一念の慈祥は
一七八、陰謀怪習、異行奇能は
一七九、語に云う、<ookagib/>山に登りては
一八〇、功業に誇逞し
一八一、忙裡にかんを偸まんことを
一八二、己の心を昧まさず
一八三、官に居るに二語あり
一八四、富貴の地に処しては
一八五、身を持するは
一八六、小人と仇讐することを休めよ
一八七、縦欲の病は医すべくして
一八八、磨礪は当に百煉の金の如く
一八九、寧ろ小人の忌毀するところと為るも
一九〇、利を好む者は
一九一、人の恩を受けては
一九二、讒夫毀士は
一九三、山の高峻なる処には
一九四、功を建て業を立つる者は
一九五、世に処しては
一九六、日既に暮れて
一九七、鷹の立つや睡るが如く
一九八、倹は美徳なり
一九九、払意を憂うることなかれ
二〇〇、飲宴の楽しみの多きは
二〇一、世人は心の肯う処を以て
二〇二、盈満に居る者は
二〇三、冷眼にて人を観
二〇四、仁人は心地寛舒なれば
二〇五、悪を聞いては
二〇六、性燥に心粗なる者は
二〇七、人を用うるには
二〇八、風斜めに雨急なる処は
二〇九、節義の人は
二一〇、士大夫、官に居ては
二一一、大人は畏れざるべからず
二一二、事やや払逆せば
二一三、喜びに乗じて
二一四、善く書を読む者は
二一五、天は一人を賢にして
二一六、至人は何をか思い
二一七、口は乃ち心の門なり
二一八、人を責むる者は
二一九、子弟は大人の胚胎なり
二二〇、君子は患難に処して憂えず
二二一、桃李は艶なりと雖も
二二二、風恬らかに浪静かなる中に
菜根譚後集
一、山林の楽しみを談ずる者は
二、水に釣るは逸事なり
三、鶯花茂くして
四、歳月は本長くして
五、趣を得るは多きに在らず
六、静夜の鐘声を聴いては
七、鳥語虫声も
八、人は有字の書を読むを解して
九、心に物欲なければ
一〇、賓朋雲集し
一一、個中の趣を会し得れば
一二、山河大地も
一三、石火光中に、長を争い
一四、寒燈ほのおなく
一五、人肯て当下に休せば
一六、冷より熱を視て
一七、富貴を浮雲にするの風ありて
一八、競逐は人に聴せて
一九、延促は一念に由り
二〇、これを損してまた損し
二一、都て眼前に来たるの事は
二二、炎に趨り勢に付くの禍は
二三、松澗の辺、杖を携えて
二四、色欲は火のごとく熾んなるも
二五、先を争うの径路は窄し
二六、忙処に性を乱さざらんとせば
二七、隠逸の林中には栄辱なく
二八、熱は必ずしも除かずして
二九、歩を進むるの処
三〇、得るを貪る者は
三一、名に矜るは
三二、寂を嗜む者は
三三、孤雲、岫を出づる
三四、悠長の趣は
三五、禅宗に曰く、<ookagib/>饑え来たりて
三六、水流れて而も境に声なし
三七、山林は是れ勝地なるも
三八、時、喧雑に当たれば
三九、蘆花被の下、雪に臥し
四〇、こん冕の行中
四一、出世の道は
四二、此の身、常にかん処に放在せば
四三、竹籬の下、忽ち犬吠え
四四、我、栄を希わずんば
四五、山林泉石の間にしょうようして
四六、春日は気象繁華にして
四七、一字をも識らずして
四八、機動く的は
四九、身は不けいの舟の如く
五〇、人情、鶯の啼くを聴けば
五一、髪落ち歯疎にして
五二、其の中を欲にする者は
五三、多く蔵する者は厚く亡う
五四、易を暁窓に読んで
五五、花、盆内に居れば
五六、世人は只だ我の字を
五七、老より少を視れば
五八、人情世態は、しゅっ忽万端
五九、熱閙の中に一冷眼を着くれば
六〇、一の楽境界あれば
六一、簾ろう高敞にして
六二、成の必ず敗るるを知れば
六三、古徳云う、<ookagib/>竹影、階を掃うも
六四、林間の松韻、石上の泉声
六五、眼に西晉の荊榛を看て
六六、心地の上に風濤なければ
六七、峩冠大帯の士も
六八、魚は水を得て逝いて
六九、狐は敗砌に眠り
七〇、寵辱、驚かず
七一、晴空朗月、何れの天か
七二、纔に筏に就いて
七三、権貴竜驤し、英雄虎戦す
七四、物欲に覊鎖すれば
七五、胸中既に半点の物欲なければ
七六、詩思はは陵橋の上に在り
七七、伏すこと久しきものは
七八、樹木は根に帰するに至って
七九、真空は空ならず
八〇、烈士は千乗を譲り
八一、世味を飽き諳んずれば
八二、今人専ら念なきを求めて
八三、意の偶会するところ
八四、性天澄徹せば
八五、人心に個の真境あり
八六、金は鉱より出で
八七、天地中の万物
八八、神酣なれば、布被の窩中にも
八九、纏脱は只だ自心に在るのみ
九〇、斗室の中、万慮都て捐つれば
九一、万籟寂寥の中
九二、白氏云う、<ookagib/>身心を放ちて
九三、雪夜月天に当たれば
九四、文は拙を以て進み
九五、我を以て物を転ずる者は
九六、理寂なれば則ち事も寂なり
九七、幽人の清事は総て自適に在り
九八、試みに未だ生まれざるの前に
九九、病に遇いて後に
一〇〇、優人、粉を傅けしゅを調え
一〇一、風花の瀟洒、雪月の空清
一〇二、田父野叟は
一〇三、心に其の心なくば
一〇四、笙歌正に濃やかなる処
一〇五、把握未だ定まらざれば
一〇六、寂を喜み喧を厭う者は
一〇七、山居すれば、胸次清洒にして
一〇八、興、時を逐うて来たりて
一〇九、人生の福境禍区は
一一〇、繩鋸も木断ち、水滴も石穿つ
一一一、機息む時、便ち月到り
一一二、草木纔に零落すれば
一一三、雨余に山色を観れば
一一四、高きに登れば人をして
一一五、心曠ければ
一一六、風月花柳なければ
一一七、一身に就いて一身を了する者
一一八、人生太だかんなれば
一一九、人心多くは動処より真を失う
一二〇、子生まれて母危く
一二一、耳根はひょう谷の響を投ずるに似て
一二二、世人は栄利の為に
一二三、花は半開を看、酒は微酔に飲む
一二四、山肴は世間の灌漑を受けず
一二五、花を栽え竹を種え
一二六、山林の士は、清苦にして
一二七、分にあらざるの福
一二八、人生は原是れ一傀儡なり
一二九、一事起これば則ち一害生ず
一三〇、淫奔の婦は、矯して尼と為り
一三一、波浪の天を兼ぬるや
一三二、人生は一分を減省せば
一三三、天運の寒暑は避け易きも
一三四、茶は精を求めずして
一三五、釈氏の随縁、吾が儒の素位
解 説
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
藤月はな(灯れ松明の火)
金吾
スプーン
wiki