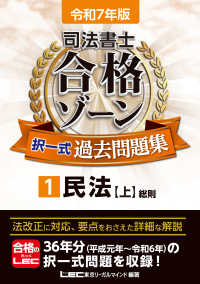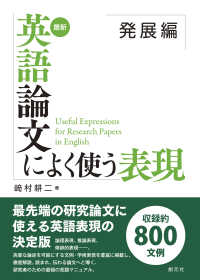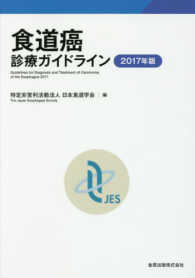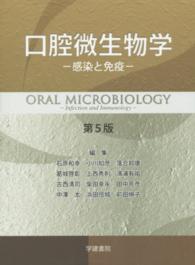内容説明
本書は、世界的なキュレーターであり、現代アート界で最も影響力のある名士録「POWER100」の上位常連であるハンス・ウルリッヒ・オブリストが、「キュレーション」という概念の黎明期に活躍したキュレーターの先駆者11名に行った貴重なインタビュー集であるとともに、現代アートの“システム”がつくられるまでの歴史そのものです。
1960年代から1970年代の初期インディペンデント・キュレーティングから、実験的なアートプログラムの台頭、ドクメンタや国際展の発展を通じてヨーロッパからアメリカにキュレーションが広がっていった様を、オブリストが鋭く深く鮮やかに描き出しています。キュレーターという職業がどのように成立してきたか、展示の方法や展覧会の作り方はどのように進化してきたか、今後キュレーションはどのような方向へ向かうのか。アートとキュレーションの関係を考える上で不可欠な1冊です。
ここ10年ほどで、展覧会の歴史というものが見直されるようになったとき、大きく見落とされてきたのは、キュレーターやアーティスト、そして関連機関同士の横のつながりです。オブリストのインタビューが興味深いのは、まさしくこの点を明らかにしており、個々人の輝かしい功績の描写にとどまらないところです。
──本書序文(クリストフ・シェリックス)より
ハンス・ウルリッヒ・オブリストは、この先に広がるアートの展望を照らす案内人でもあるのだ。
──本書後記(ダニエル・バーンバウム)より
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koichi Tamura
4
現代アートを作った、そうそうたるキュイレーターのインタビューのまとめ。 海外のキュレーターはあまり知らないので、そういう意味では良かったが、もっと調べながらじっくり読まないと厳しいですね。2014/03/26
hamama
1
語り手はいつまでもいるとは限らないと改めて。2015/06/25
TAKAMI
1
コンテンポラリーアートをつくったスターキュレーターたちへの貴重なインタビュー集。これを読むと近代アートにどういう歴史があり、その中でどう新しい取り組みにチャレンジしてきたかが断片的にはわかるが、いかんせん知識がなさ過ぎてついていくのに精いっぱい。その中でも共通して出てくるアーティストやキュレーター、批評家や歴史家の名前から、少しずつ形が見えてくるかな、という。コンセプチュアルアートの歴史を改めて勉強し、また読み返してみたい。2015/05/22
st
1
面白い時代に面白く生きたレジェンドたちの物語。さて、今の時代を自分は面白く生きたていけるか?(ちなみに、この本「攻殻機動隊」のように欄外のネタがポイント)2014/12/07
ayaMurakami
0
キュレーターのオーラルヒストリー。拾い読みも楽しい。2017/05/30