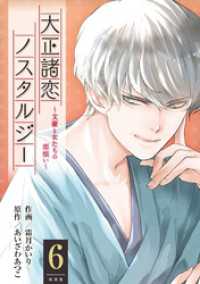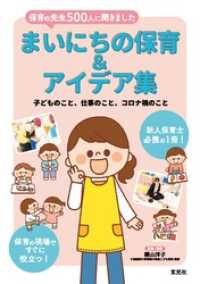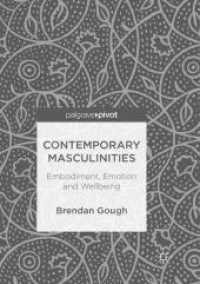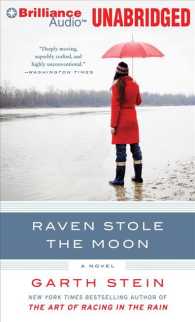- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
気の合う仲間とだけでは、成し遂げられないことがある。
職場でも取引先でも地域でも多様な人との協働が必要な時代。
政府、市民、ゲリラまでも巻き込み困難な状況に向き合った著者から学ぶ前進の方法。
「対話は必ずしも最善の選択肢ではない」
世界50カ国以上で企業の役員、政治家、軍人、ゲリラ、市民リーダー、コミュニティ活動家、国連職員など多岐に渡る人々と対話をかさねてきた、世界的ファシリテーターが直面した従来型の対話の限界。
彼が試行錯誤のすえに編み出した新しいコラボレーションとは。
・部署間や取引先との協働を進めたいと願う企業の担当者、マネジャー、経営者
・新製品・サービス開発、新規事業、イノベーションなどを担う担当者
・組織内外にネットワークを広げ、連携を図る人
・対話ファシリテーターや組織開発・コミュニティ開発のファシリテーターなど
職場から、社会変革、家庭まで、意見の合わない人と協働して成し遂げなくてはならないことのある、すべての人へ。
相手と「合意」はできなくても、異なる正義を抱えたままでも、共に前に進む方法。
SNSを開けば自分と同じ意見が流れ、住む場所や働く相手も、自由に選びやすくなった現代。
仲間を見つけやすくなった反面、自分とは異なる人を「敵」にするのも容易になっている状況だからこそ、意義深い1冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
58
コラボレーションから想像するものがある。それとは、一線を画す内容で興味深い。確かに、そんなに筋書き通りである筈がなく、それは自分自身もそうなのだということを気づくかどうかがある。共通の課題認識があれば、そこから少しずつ進んでいくこと。途中にある小見出しが響く「創造性にはネガティブケーパビリティが必要」としてピカソの創造のことが語られている。なるほどと思うし、数年前から、自分の中で、とても大切な言葉となっている。2023/12/14
Koichiro Minematsu
26
著者の本は何冊か読んでいての、このタイトルで思わず手にした本でしたが、世界的ファシリテーターが取り組んできた対話の事例があるからこそ、賛同できない人、好きではない人、信頼できない人と難易度が上がっても、前進できるという強いメッセージがある。従来型コラボレーションではない、ストレッチ・コラボレーション。失敗であっても主張、関わりを続けること。2019/01/23
mft
10
対立する集団がそれでも一緒に進まなければならない状況で、何ができるか。すぐに対話という発想にはなるが力関係によっては成り立たない場面もある。みんなで一つの方向を向いた計画に同意できなくても、ビジョンは共有できそこから進んでいける。というようなことをストレッチコラボレーションと呼んで説明しているのだが…難しいね2020/12/29
の
9
気持ちを切り替えるのが大事ですよ、要するに、という本でした。2019/02/22
GX
7
この考え方を適用することで、従来、「強制」、「適応」、「離脱」など、コラボレーション以外のアプローチをとっていたところにまで、コラボレーションを広げていくことが可能になるような気がします。また、この本を読んだあと、すぐに読んだ「私とは何か『個人』から『分人へ』と合わせて考えることで、敵のなかにも「分人」を想定し、そことのコラボレーションから始めていく、ということも可能なように思いました。最近、別々の本と本とつながりに巡り合うことが、しばしばあって、それも、本を読む楽しみの一つになっています。2018/11/25