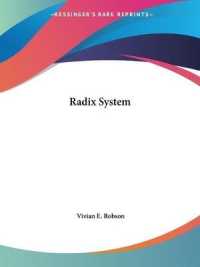内容説明
外国では、退位した王・皇帝に特別な呼称はない。それは、王・皇帝という地位に権威・権力が付随し、いったん退位すれば、その権威・権力はすべて次の王・皇帝に引き継がれるからである。ところが日本では、退位した天皇は「上皇」と呼ばれ、ときに政治の実権を掌握してきた。上皇による政治=「院政」という言葉は、引退しても権力を手放さない実力者のあり方を指す表現にもなっている。では「上皇」とは、どのような存在だったのか? 200年ぶりの天皇譲位を前に、上皇の歴史を辿り、現代における天皇・皇室、そして日本と日本人を考えるための視座を提示する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さつき
56
帯の200年ぶりの天皇譲位という言葉に驚きました。最後に譲位があってから、それだけ経っているんですね。著者が幾度も述べている日本ではタテマエよりもホンネ。地位よりも人物、は院政をしく上皇を象徴してますね。院政を支えた中級貴族の実務官についてなど新たな視点で歴史を見られました。皇統は足利義満の時代よりも、織田信長の時の方が危機的状況だったというのも面白く説得力を感じました。明治以降については、編集者の質問に答える形での著述。まだまだ書きにくいテーマなんでしょうね…2018/09/21
chisarunn
10
平成が終わって天皇陛下が上皇陛下になられた時、それって昔の「ゴシラカワ」とか「ゴダイゴ」とかとどう違うの?って反射的に考えませんでした?いやいや、今は天皇陛下が政治を廻してらっしゃる訳じゃないから違って当然ですけど。でも理路整然と説明できないよね。そこでこのご本!昔の上皇陛下がいつ頃からどういう風に統治してらして、それはなぜなくなったのかわかりやすく、面白い文章で丁寧に説明されている。そうか、院政ってこういうことだったんだ、とわりかし(ほかの時代よりは)知ってるつもりだった自分もいっそう理解が深まった。2022/06/13
うろん
8
歴史上の上皇、太上天皇についてどんな役割を果たしてきたのかを知りたくて読みました。2019/11/13
田中峰和
4
摂関に対抗するため生まれたとされる院政。天皇に娘を嫁がせ皇太子にして政権を簒奪する藤原氏に対する手段として、跡継ぎの皇子を天皇にして自らは上皇になるのは、旨い手である。歴史を辿れば天皇はいつもお飾りで、武士の台頭によって将軍は天皇を利用する上皇を禁じようとした。皇室に敬意を払っていたとされる信長も、自らを国王あるいは神と考えだして、右大臣以降の就任は拒否していた。南北朝に分かれていた鎌倉後期、後醍醐天皇は、上皇になって南朝で権力独占しようとしたが、それもかなわず。長い武家政治が終わり、維新で神となった。2020/05/31
Yam
4
日本史の授業というと、史実をひたすら覚えるのみで、どのような仕組みで歴史が動いてきたのか学ぶことはできなかったように思います。この本では上皇という存在を軸にどのようなシステムで政治が行われてきたのか理論的に説明されていてとても面白かったです。史料が少なく、推測に頼るしかない部分はあると思いますが、研究が進み歴史の世界がどんどん明らかになっていって欲しいです。2019/11/17
-

- 電子書籍
- この恋を選んだ理由~アルファの執愛【全…
-
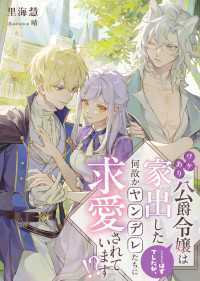
- 電子書籍
- ワケあり公爵令嬢は家出した……はずでし…