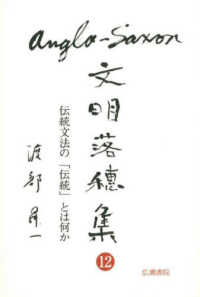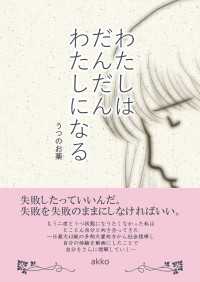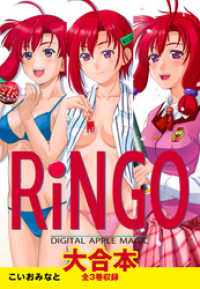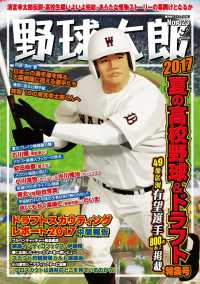内容説明
聖人の遺体や遺骨・遺灰、聖人が身にまとったものや触れたものは「宝石や黄金より価値がある」とされ、芳香や光を放ち、腐敗しないと信じられた。死人を蘇らせ、病気や怪我を治し、現世の罪を清めて天国に導く力を持つとされた聖遺物。教会はその聖性と効験を、聖堂の装飾、祭壇画や黄金のシュライン(聖遺物容器)などさまざまな造形で民衆に訴えかける。救済と奇跡を求めたキリスト教社会の熱狂と芸術への昇華の過程を辿る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
刳森伸一
5
キリストや聖人にまつわる道具や肉体を聖遺物として崇敬の対象として扱ってきた中世のキリスト教徒たちの心性の歴史を追う。崇拝と崇敬の違いから始まり、聖遺物の受容、聖遺物が持つパワー(ウィルトゥス)、聖遺物を入れる容器の聖遺物化、聖遺物にまつわる狂気的なエピソードなど、どれを取っても面白い。同種の本も少なく、非常に価値のある一冊だと思う。2021/05/17
Homo Rudolfensis
5
☆4.0。かなり面白い。当初、聖遺物は聖遺物として崇敬の対象でした。ところが、ご利益を求めた民衆が見せることを要求するようになったため、展観用の保管容器が必要になりました。そして、容器の中の聖遺物の価値を証明するために、容器は段々と豪華なものになっていきました。すると今度は容器そのものが崇敬の対象となっていきます。更に、そうした容器などを描いた芸術作品も聖性を宿したものと見做されるようになります。2021/05/06
rinakko
5
“キリストやマリアに限らず、諸聖人に関しても、(略)存在していてもおかしくないと思われる聖遺物は、そのほとんどが存在したことになっていったと言っても過言ではないようだ。(略)いずれにせよ、聖遺物崇敬の「演出者」たちは、大変豊かな想像力と細部に至る読み込みでもって、きわめて優れたテクスト・クリティークを行なっていたとも言えるだろう。” “一人の聖人の遺体が、無数に分割され、欧州全土に流布し、至るところの教会に安置された様子は、喩えて言えば、今日のATMに近いところがある。(略)聖人は2021/04/29
maqiso
2
中世ヨーロッパでは聖遺物が聖人以上に熱心に崇敬され各地の教会に奉遷されていたが、見た目では価値が分からないため、聖遺物容器が豪華で具体的なイメージを喚起するものになった。聖遺物が聖である理屈とは別に、近づきやすさやイメージのしやすさによって信仰が栄えていたのが面白い。墓泥棒や分割で手に入れた遺体が教会の中心となるのが異様だ。2019/07/14
NyanNyanShinji
0
本を読むことで知らないことを知ることは楽しい。本書の冒頭はキリスト教にまつわるショッキングな事から始まる。テューリゲンの聖エリザベートの遺体の埋葬前に、善男善女の一群が彼女の遺体を包んでいた布を切り取り引き裂き持ち持ち帰り、挙句に彼女の髪や爪、耳や乳首までもぎり去った者もいたという。 聖遺物とは亡くなった聖人がかって持っていた聖性が、その体の一部や彼が身に纏ったもの・触れた物にも伝わという考えに基づくものである。また聖遺物自体の劣化を防ぐために、その聖遺物の形を象った容器に関する記述も含めて面白い本だった2023/03/25