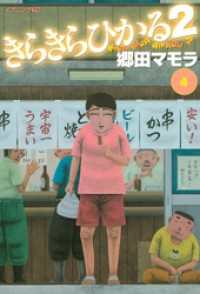内容説明
対照的な文学的軌跡をたどりながら、最終的にはともに自死を選んだ芥川龍之介と太宰治。「近代的自我」の問題を問うた福田恆存が、その問題意識から二人の傑出した作家に見出したものは何だったのか。初期の作家論を代表する「芥川龍之介I」をはじめ、戦後に書かれた「芥川龍之介ll」、太宰の死の前後に書かれた二つの評論を所収。独自の視点で描かれた傑作文芸評論集。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
134
太宰と芥川自身の著作はかなり読んでいて新鮮な読み方が既に出来ないから、時々、指南役が欲しくなってこういう本を探して読む。二人がなぜ書いたか、なぜこのテーマか、なぜその時にそういう選択をしたか、なぜ死を選んだか、ということが述べられている。芥川については納得するところが多い。大宰に対しては、作者より少し年上なだけであろうか、これだけ成し遂げたのになぜ?という視点があるように思った。まあ、作品だけ見れば、二人ともそんなに難しいことを書いていないのだから、単純に、作品を読んで味わえばそれでいいのだろう。2019/07/07
ころこ
40
本書は①芥川Ⅰ、②芥川Ⅱ、③太宰の3つの文章で構成されている。本書の半分の長さである①は、著者の心象風景であり、芥川を捉えようとしていない。我々の時代にはみえているものが、前時代の人にはみえていないということは往々にしてある。例えば世紀末に人々は何をみていたかを想像すればよい。「です、ます調」の②はうって変わって読める。②と③との対比で本書は読むことができる。②著者は芥川を「真空」と例える。芥川にとって「私」の代わりになるのは、著者が「さっと風が吹き立ったあとの人間のうしろ姿の寂しさ」と表現した「比喩」で2023/01/16
かふ
19
初期に書かれた「芥川龍之介Ⅰ」を読んであまりにも衒学的で精神的な評論で正確にはよくわからなかったが『芥川龍之介Ⅱ』ではその反省からなのかかなり論理の要点を簡潔にまとめて書かれたいるので評論としてはⅡの方がいいと思うのだけど著者が言いたかったことはⅠなのだ。芥川が比喩でしか文学を語れなかったというのは、古典文学の枠組みで自身の文学はその絵の中にという。そこが自然文学派(白樺派)の私小説とは違い安易な自己表出(エゴイズム的な私小説のリアリズム)を避けていた。2020/02/18
しゅん
13
虚構から告白、告白から虚構、生から死、死から生。芥川と太宰の道行きはたしかに逆行しているかにみえたが、最終的にはともに自死を選んだ。ついでに写真のポーズと髪型も似てた。ここにあるのは作品分析というより、作品から受け取った意味の分析。つまり、福田その人の社会と芸術との対峙を問うており、小林秀雄の私批評を想起せざるを得ない。しかし、ここまで自己の観念を他者を借りて絞り出すことが今の世で受け入れられるだろうか。牽強付会の誹りを免れないのではないか。そうした時代の変化が良いことか悪いことか、よくわからない。2020/07/16
yuma6287
6
教科書のウラ側。昭和初期に自殺を選んだ2人の作家を選び、それぞれの本質に迫った一冊。作品の知識と洞察力の高さから繰り出される人物評に、受験勉強でほんのり培った作家像が大きく変化した。文明開化に持ち込んだ西洋の文学が、換骨奪胎出来ないでいた事、2人してキリスト教的考えに動かされた事、自殺が単なる自殺では無い事が印象的。龍之介の1は非常に難解だが、それ以外は読みやすい為、作品の副読本として抑えておくのはありだと思う。語句の解説一覧が無い事に腹が立った。2024/06/19