内容説明
藤原道長が恐れ、紫式部を苛立たせた書。それが随筆の傑作「枕草子」だ。権勢を極めてなお道長はなぜこの書を潰さなかったのか。冒頭「春はあけぼの」に秘められた清少納言の思いとは? あらゆる謎を解き明かす、全く新しい「枕草子」論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nico🐬波待ち中
104
表題がなんとも魅惑に満ちている。中宮・定子の毅然とした美しさや聡明さ、それを見守る清少納言の知性に惚れ惚れする。清少納言好きはもちろん、平安時代好きにはたまらない一冊。とても贅沢で有意義な時間を過ごせた。千年の後の世でも受け入れられ、幅広い世代に読み続けられている『枕草子』。定子が後宮で創り上げた文化は時代を超えて今もなお生き続ける。『枕草子』に託した清少納言の”たくらみ”は大成功と言えよう。悲しい時こそ笑いを。くじけそうな時にこそ雅びを。「あはれ」を「をかし」に変える清少納言の姿勢を見習いたい。2021/01/16
はる
85
とても興味深い内容で楽しめました。「枕草子」といえば軽い身辺雑記の随筆というイメージ。だがその裏には清少納言の巧妙な仕掛けが隠されていた…。清少納言の仕えた中宮定子は不遇な人生でした。その定子の心を慰めるため、定子の素晴らしさを永く知らしめるため…。枕草子に込めた清少納言の一途な想いが切ない。読み進めるに従い清少納言と「枕草子」の実像が明確になります。「枕草子」の本質を見抜いていたに違いない、紫式部の言葉に心が震えました。2019/01/17
ちゃちゃ
83
『枕草子』は、24歳という若さで不遇の内に崩御した主(あるじ)定子への「挽歌」だった。山本淳子氏の主張は斬新でかつ説得力に溢れている。才気煥発、ネアカで鋭い感性と機知を身につけたとされる清少納言。定子の父道隆が亡くなり、長徳の政変以降没落の一途を辿った中の関白家にあって、清少納言は定子を中心とした文化サロンの賛美に終始する。その「たくらみ」はどこにあるのか。悲しいときにこそ笑いを、くじけそうな時にこそ雅びを。歯を食いしばり万感の思いを込めて綴った、敬愛してやまない定子への鎮魂の書、それが『枕草子』だった。2017/04/23
初美マリン
57
皇后定子の理想的な人生として、決して惨めではなく、後世に伝えるために書かれた、あるいは捧げるために、枕草子は、あった。なんか清少納言が、けなげで一途で芯のある女性に思えた2018/07/14
kagetrasama-aoi(葵・橘)
49
新潮社の古典文学集成の「枕草子」(訳註は萩谷朴氏)を枕元に置き、就寝前に少しずつ読む「枕草子」大好きの私には堪らない作品でした。一条天皇と定子皇后の愛を間近で見た清少納言が、どんな気持ちで書き上げたのかが詳しく考察されていて、納得したり涙したり…。そして、終章の定子皇后のお和歌で、涙涙でした。悲運の皇后でしたが鮮やかな生き様が、清少納言によって現代の私達にまで知られています。そんな腹心の女房に出逢えたことは、僥倖だったんではないでしょうか。読み終えてそんな感想を抱きました。2021/10/13
-

- 電子書籍
- 神様のしっぽ 1 光文社 BL COM…
-
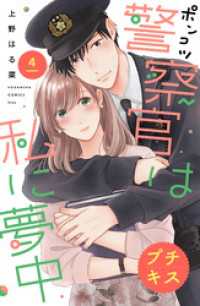
- 電子書籍
- ポンコツ警察官は私に夢中 プチキス(4)
-
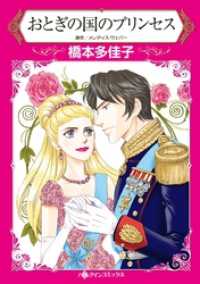
- 電子書籍
- おとぎの国のプリンセス【分冊】 10巻…
-
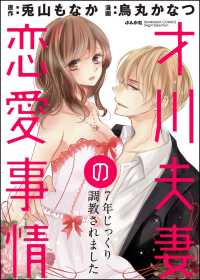
- 電子書籍
- 才川夫妻の恋愛事情 7年じっくり調教さ…





