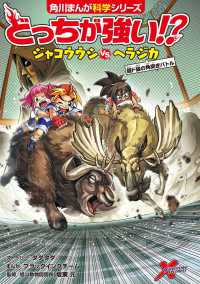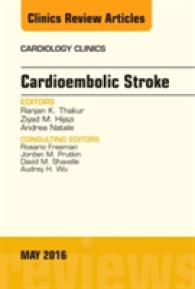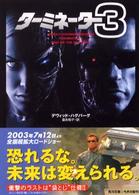内容説明
大宝元年(七〇一)、藤原不比等の子として生まれ、同い年の聖武天皇と同じ邸宅で育った光明子。やがて皇后となり、天武―文武―聖武と続く皇統の維持が最大の使命となる。だが、長屋王の変、相次ぐ遷都、身近な人々の死など、動乱の荒波は彼女にひとときの安らぎも与えることはなかった。「稀代の女傑」か、慈悲深い篤信の女性か。毀誉褒貶半ばする光明皇后の心奥まで光を当て、天平のヒロインの実像にダイナミックに迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かごむし
31
あの藤原不比等の娘で、あの聖武天皇の皇后で、あの孝謙天皇のお母さん。要するにお前だれやねんシリーズ。通説に対して、疑義を唱えたりと踏み込んだ内容になっているが、通説自体が初耳なので、ふむふむとうなずくだけだった。平城京や、聖武天皇建立の大仏、当時の天皇を取り巻く政治体制など、知ったからどうということはないにしても、こういう雰囲気だったのね、ということがわかっただけでも読んで損のない読書だった。昔は女性天皇いっぱいいるじゃないかと思っていたけど、あくまで正統な男性天皇への中継ぎだったとか、なるほどなあと。2019/04/18
黒猫
14
藤原不比等の娘として生まれ、藤原氏が天皇との結び付きを深め、四兄弟を中心に政治力を強めていく中で、天平の時代に深慮深く冷静で知的な高貴な女性が存在していた事実に深く感動する。不比等の娘として、聖武天皇の后として藤原氏と天皇の結び付きの役を担い、藤原四兄弟の急激な勢力拡大を心配しながらも的確にそれを支え、天然痘による四兄弟の相次ぐ死に不安を抱えながらも、目まぐるしく政権が変化する中で常に冷静。聖武天皇を支え、仏の帰依心を持ち施薬院、悲田院を置き、民の社会福祉に慈悲の心を持って接した。慈悲深く先進的な女性。2020/10/10
tsubomi
12
2018.02.15-05.10:聖武天皇と同じ年に生まれ、妃となった光明子。藤原一族から宮廷へ入った女性としての苦労や気遣い、幼馴染である聖武天皇とは基本的にペアで行動していたこと、難波宮や紫香楽宮造営のこと、大仏に込めた願いなど、詳細に解説されてあり、この時代に生きた人の価値観や暗部について知ることができましたが、資料が少ないのに著者が自説を断定的に述べたり、発掘された物証については信用できないと述べているあたりは独断的で好きになれなかったです。あくまでも書き方の問題でしょうけれど。2018/05/10
びっぐすとん
12
図書館本。新聞書評みて。光明皇后といえば皇族以外で初めて皇后になり、らい病の貧民の体を拭いた慈悲深さ伝承とか聖武天皇と夫唱婦随だったとかしか知らなかったが、先例のないことばかりの人生は苦労も多かっただろうな。病弱な夫を支え、夫の死後も家族・国(会社)の為に頑張る妻。今でもこんなお母さんいるよね。女は強い。娘の皇極天皇は両親の娘を思うあまりの刷り込みが行き過ぎて、頑なな女性になってしまったようだけど(こういう人、今もいる)。男子血統しか即位出来ない故の犠牲者でもあるな。何だか今の皇室の問題にも繋がるようだ。2017/12/12
遊未
9
両親を考えても、もっと権力志向の女性かと思っていました。逆に聖武天皇はなかなかしっかりしていらっしゃる。 それにしても周囲に人材が多いし、直系の男子に恵まれず誣告やら乱やらを乗り越えなければならない。女性らしい女性として描かれていますが、大変優れた方であったことがよくわかります。2018/03/17