内容説明
近世、全国の私塾、藩校で広がった読書会=会読、その対等で自由なディベートの経験と精神が、明治維新を、近代国家を成り立たせる政治的公共性を準備した。思想史の傑作!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
34
優雅なイメージを持ってしまうタイトルだが、江戸時代において思想集団が形成される土壌や明治時代において教育制度が整備される前段階なども知れたとても収穫の多い一冊でした。日本には討論の歴史がないなどという話を聞くこともありますが、まったくそんなことはなく当時の読書会、会読は討論が多かったそうです。というのも江戸時代は身分について厳しい決まりがあり、下級武士が上級武士に意見するというのは普通できませんでした。しかし、読書会においてはそれが許され、討論により勝敗をつけていました。2022/03/23
bapaksejahtera
22
年少期に素読、長ずるに及び講義を授かる江戸初期の教育。学問が立身出世には繋がる中華朝鮮とは異なり、我が国では学問のあり方は独特の形をとる。中期以降会読方式の学習法が生ずる。疑似兵営体制である武士支配が、偃武後に生ずる財政迫等問題対処の人材発掘を求められ、幕府は学問所、各藩は藩校の設立を進める。その教育に会読が用いられる。しかし本来自由な思想活動を促すこの方式は幕末に至り次第に多くの結社叢生に繋がる。維新政府の設立後暫時はこの方式が用いられるが、国制の強化には輸入された師範教育が優先され会読は消滅する。良書2023/04/18
樋口佳之
22
会読という形式の持った意味合いを語るとても興味深いお話。学ぶ形式において近代に接続していると言うか、現代を凌駕しているかも。新書レベルに整理して出版して欲しかった。2018/10/02
さとうしん
20
読書が科挙を通じて立身出世の手段となる中国・朝鮮とは異なる環境だったからこそ、日本でスポーツゲームのように討論しながらともに書物を読み進める会読が発展した、明治に入って学問が立身出世の手段として位置づけられると、効率的なカリキュラムに沿った一斉講義の手法が導入され、学校から会読が退けられ、廃れていったという経過を見ると、「勉強は何のためにするのか」「実学とは一体何なのか」ということを考えさせられる。日本の教育の将来について考えるのに参考にするべき本だと思う。2018/10/10
Nobu A
19
前田勉著書初読。18年刊行。近年学校でも社会人の集まりでも時好の読書会。その起源を知りたく手に取った。古語で綴ったのも含む数多な資料を揃えた学術書寄りの本書。欧米では16世紀頃から親しまれてきたのに対し、日本では江戸時代を起原とする読書会。当時は「会読」と呼ばれ、全国各地の藩校で素読、講釈、会読と確立した学習方法の一つとして普及。門閥制度が幅を利かせた江戸時代、福沢諭吉も立身出世の為に会読を通して儒学や蘭学を学んだとか。明治時代に全盛を迎え、その後は師範学校の体系的教授法や演説の流行で衰退。流し読み読了。2024/08/23
-
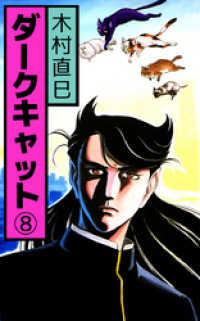
- 電子書籍
- ダークキャット 8巻 まんがフリーク
-
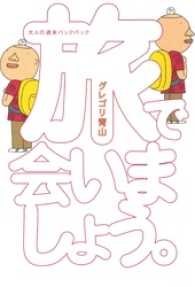
- 電子書籍
- 旅で会いましょう。 - 大人の週末バッ…
-
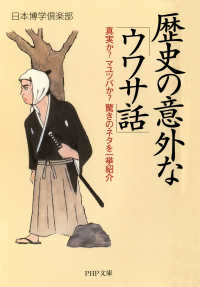
- 電子書籍
- 歴史の意外な「ウワサ話」 - 真実か?…
-
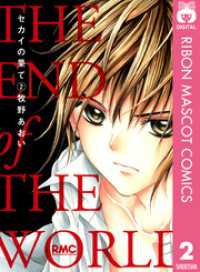
- 電子書籍
- セカイの果て 2 りぼんマスコットコミ…
-

- 電子書籍
- 武装錬金 9 ジャンプコミックスDIG…




