内容説明
「シンギュラリティ」「IoTで豊かな未来」「鉄腕アトム」「ターミネーター」……私たちは、機械を愛し、憎んでいる。では機械のほうから「私たち」を見たらどうなる? テクノロジーで拡張し変容した私たちの姿を、「将棋電王戦」から科学技術論などを横断しながら見つめ、「人間」観の刷新を企図する試み。気鋭の人類学者が、「現在のなかにある未来」を探る、通快かつ真摯な思考!
目次
第一章 現在のなかの未来
第二章 ソフトという他者
第三章 探索から評価へ
第四章 知性と情動
第五章 強さとは何か
第六章 記号の離床
第七章 監視からモニタリングへ
第八章 生きている機械
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
37
【人新世11】これはもしかしたらすごい本かもしれない。カニバリズムとは食人のこと。機械が人を食べるのだ。端的にはAIが人を食べる=影響を与えることによって、人間が変わる=人間でなくなる。近年の(存在論的転回後の)文化人類学が非近代社会で見出したカニバリズムとは、他者を食べることにより自己を他者としてつくりあげること。これをAIと人間の関係に適用する。人間の知能を超えたAIの出現により人間はどうなるのか。ニック・ボストロム【人新世8】は人類滅亡と答え、それを防ぐためにAIコントロールの研究に着手せよと↓2021/01/14
Tenouji
15
不確実性が全くない世界で、「私」は存在可能なのだろうか…『人となりては童のことを捨てたり』。AI以降、人は人のことを捨てることになるのか…梅田氏『ウェブ進化論』の将棋の革新の話しは、感動して読んだ記憶がある。その後のAI将棋の展開について考察が、本書は秀逸。人間とAIの共進化を感じさせる、一方で、SNSにみる再帰的自己の不安定性は、私の固有性を溶解させていく。そう、これは、あの『ゴースト』の考察である。2020/03/01
無重力蜜柑
13
人が機械を使うのか、機械が人を使うのか。技術の哲学の分野ではこうした対立を伝統的に道具説と自律説の対立という(ちなみに筆者はp.15で社会的構成論を道具説の類似概念としているが、これは明確に誤り)が、それに対し筆者は人間と技術が結び付き新たなアクターへ「生成」されるという媒介説の立場をとる。機械の論理でも人間の論理でもなく、両者がハイブリッドされた機械―人間の論理。こうした思考自体はそこまで目新しくもないが、本書はその生成の様を文化人類学の細密な筆致で描き出すあたりに、空理空論を超えた面白さがある。2024/04/27
msykst
12
「一なる自然と多なる文化という二項対立の放棄」という現代人類学の発想を、AIと人間の将棋対局やネットコミュニケーション等々、機械技術と人間が交錯する題材に敷衍する。「機械」と「人間」の区別、それに基づく「機械」と「人間」の関係、あるいは知の体系全般、等々、近代社会の前提が根底から解きほどかれ、たゆまぬ変容のプロセスに投げ入れられる。読む時期が遅くなってしまったけど、『内在的多様性批判』と併せて精読しなければと思った。2025/09/28
kenitirokikuti
10
最近流行りのヴィヴェイロス・デ・カストロの存在論的転回をヒトとAIでやってみようという内容。半分くらい将棋の電王戦を扱っていて分かりやすい。もう半分は朝井リョウ『何者』の読み解き。著者も将棋アマ初段ぐらいだそうです。2018/10/06
-
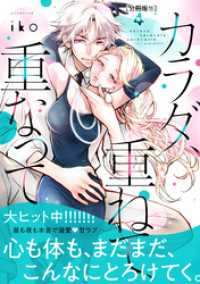
- 電子書籍
- カラダ、重ねて、重なって 分冊版(15)







