内容説明
この世の悪は、一人ひとりがその行いを改めれば払拭できるものだろうか? 自然災害に見舞われ、多くの人が苦しめられているとき、そこに悪の問題はないのだろうか? 孔子や孟子、荘子、荀子などの中国古代の思想家たちも、悪という問題に直面し、格闘してきた。清代にいたるまでの、そうした悪をめぐる哲学的思考を辿りなおし、その可能性と限界を描き出す。悪にあらがい、その残酷さを引き受け、乗り越えるための方途を探る哲学の書である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たかしくん。
27
朱子学、陽明学の悪に対する考え方の相違点から始まり、中国の根底となる古代思想を探っていく展開です。そもそも性善説、性悪説は本当に相反するものなのか?性善説の代表、孟子の思想とそれに近いヴォルテールを引合いにだし、「性善説の前提には、地上には悪がある」と整理しています。一方、荀子はじめ老荘思想こそが性悪説とする著者の主張に意外感はありましたが、人間の欲望を悪の根源とする前提なればこそ、人間の欲望を減らす「無為自然」に行きつくのでしょうね。2014/10/20
さとうしん
9
『悪の歴史(東アジア編上)』の内容・構成に不満を感じたので、中国史で「悪」を語るなら他にどういう方向性があるのだろうと本書を手にとってみた。先秦諸子や朱子学・陽明学を「悪」、そしてそれと対比される「善」を切り口に新たな文脈に再構成しているが、本書を読んで連想したのは、儒教を「怨念と復讐の宗教」という文脈に再構成した浅野裕一の『儒教』である。両書を対比し、同じ歴代の思想の再構成を図るなら、本書のような方向性が有意義ではないかと感じた。2017/10/12
てんちゃん
5
善の追求に対する中国思想家の考えの変遷が簡潔に纏められている。性善説と性悪説の違いこそあれ、孟子・荀子ともに、心の中に生まれる善の端緒を、きちんとした行為に繋げる努力を重要視しており、その手段として、礼の必要性が語られている。また、礼に絶対的なものは無く、時代や地域によって様々であるため、各状況に何がふさわしいかを主体的に考え、理を分有することが必要という点、多様性の重要度が増す現代社会に通ずるものを感じた。2015/01/14
はちめ
3
要するに孟子と荀子の思想が有している修正主義的な思想が現代的な悪の課題に対応できる可能性があるということで良いのだろうか?2016/10/02
ぷほは
3
以前『徳川思想小史』を読もうとして、中国思想に対する無知ぶりを自覚して以来、中国哲学について分かりやすい本はないものかと思っていたところ、「悪」という魅力的なテーマに挑んだ本書を一気読みすることとなった。平易な文体に加えメジャーな中国の思想家たちが登場する本書は、入門書としても読めるが、同時にフクシマ以降の社会への構想力という、極めてアクチュアルな問題関心に裏打ちされている。中村雄二郎『悪の哲学ノート』の次に読んだが、むしろ、サンデルの正義本などと読み比べたくなるような本だった。2015/01/11
-

- 電子書籍
- Berry's Fantasy 追放さ…
-
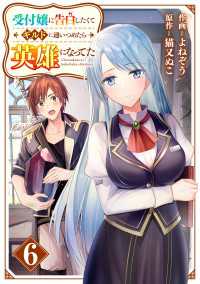
- 電子書籍
- 受付嬢に告白したくてギルドに通いつめた…
-
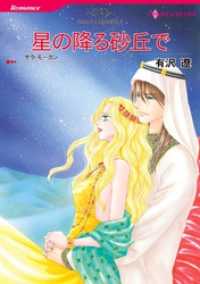
- 電子書籍
- 星の降る砂丘で【分冊】 7巻 ハーレク…
-
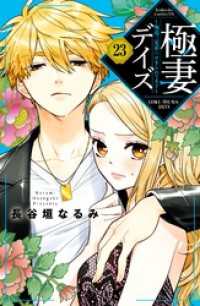
- 電子書籍
- 極妻デイズ ~極道三兄弟にせまられてま…
-
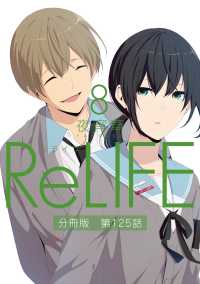
- 電子書籍
- ReLIFE8【分冊版】第125話 c…




