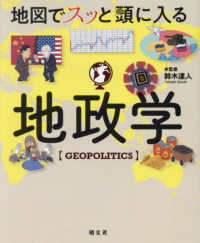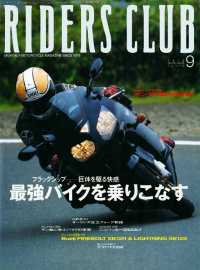- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
事件が起こるたびに、メディアで飛び交う様々な意見。専門家は、コメンテーターは、政治家は、世論調査は、こう言うけれど、本当にそうなのか? 情報の洪水を嫌でも浴びせられる現代社会で、自分の意見を持ち、ふりまわされずに生きていく第一歩は、「少数派になるのを恐れない」「わからないときには判断を保留する」「変節を恐れない」ことだ。世の中で意見が分かれる悩ましい問題を題材に、自分なりの正解の導き方をアドバイスする思考のトレーニング。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
326
タイトルから期待するものと、本書の内容とにはかなり大きな乖離がある。副題の「自分らしく考える」の「自分」を香山リカとするならば、まあだいたいそんなところだ。また、精神科医としての立場から語られたものもあるが、大半は1人のインテリゲンチァとして、現代社会の諸相を分析的な視座から思索したものである。著者としての個性は十分に発揮されていると思う。篇中で最も眼を開かれたのは、スプリッティングに関するくだりで、ブッシュ、小泉、民主党の菅(実行は蓮舫)が行った欺瞞を明らかにして見せたあたりか。2018/08/30
太田青磁
19
「役割自己の解体」というフレーズが心に残る一冊。表現の自由に対する警鐘は響くものがあります。救急医療の現場の話は医学部志向の世相とも合わせ、ものすごく考えさせられます。ふつうの人がかかれるふつうの病院がなくなっていく現実と「惻隠の情」こそが医療現場に今求められているという主張に共感しました。客観的という科学にとってのあたりまえを教育することの難しさも感じます。医者としての自分のアイデンティティにふれる最終章が切なく感じました。父親との最期の一日を自宅で過ごす経験は何物にも代えがたかったのでしょう。2013/05/05
はまななゆみ
13
何事もバランス感覚だということでしょうか。「母だって人間だからおろかな一面があって当然」というような指摘はなんだかとても腹に落ちました。2019/03/23
maito/まいと
12
タイトルに直結する内容が、読んでいくと段々遠ざかる1冊。ただそこに拘らなければ、「通説」に対する疑問を投げかけることで、思い込みを取っ払うきっかけになる要素が満載。科学で人の思考や行動を予測することはもはや難しく、周りや社会の意見や雰囲気に自分が適合できないことは罪ではない、自分が出来ることやしたいと思えることをすることが一番正解に近い、などなど。日々気疲れに苦しんでいる方には救いとなる内容かも。まあ、肝心の“らしく”が何かを見つけるのが一番難しいのだけど(苦笑)2017/10/28
ダンボー1号
11
著者自身何か悩んでいそうです。ここ10年で確かに二択を迫られるケースが多いです。2011年の本ですが今同じテーマで今書くとどうなるでしょう?振り返ると郵政民営化程度で大事だった選挙が懐かしい印象です。今は各論で二択出来ればいいのだけど・・・どちらか選べば全てがつながる怖さがあります。自分らしく縛られない生き方提唱の香山さん。クラスに一人なら問題ないけど女子の半分香山さんだと大変だ。もっとも勝山さんも同じか。現在の不人気も世間マスコミの左寄りの反動の様な印象です。2015/06/14