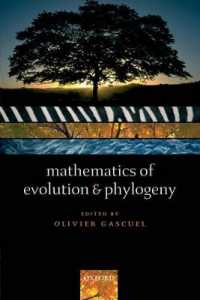内容説明
科学はストーリーに満ちている。科学研究の手法も、科学を伝えることも、何かを語るためのプロセスだ。
著者が主張するのは、現実社会における「物語(narrative)」の力を一世紀にわたって学び、応用してきた人々に対して、科学者が目を向け、その助けを求めるべきだということ。
物語によって脅かされるものは、何もない。物語は、人間の文化のあらゆる側面に浸透している。科学者たちは、科学が物語のプロセスであること、物語はストーリーであること、したがって、科学にはストーリーが必要であることを認識しなければならない。
-

- 電子書籍
- 魔王になったので、ダンジョン造って人外…
-
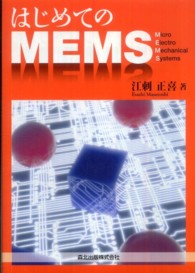
- 和書
- はじめてのMEMS