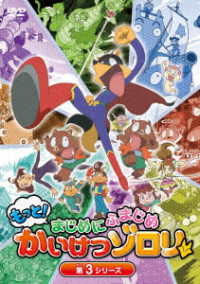- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
他の言語に較べて英語の単語数が多いのはなぜなのか? フランス語やラテン語を知ることが英語学習の早道ってホント? 作家、翻訳家として活躍する著者が、ネイティヴも目からウロコを落とす英語の歴史をお教えします。さらに、ラテン語、中国語にも精通する語学のプロフェッショナルの視点から、日本人に適した「正しい英語との付き合い方」を提案。世界中の言語にルーツをもつ英語の「生い立ち」を知れば、語学がさらに面白くなる! <ネイティヴスピーカー&英語のプロたちの声>「英語という厄介なやつを実に多角的に取り上げた本で、意外に勉強になるところもあり、同感する部分と若干異を唱えたい部分がありますが、著者と言葉の話をしたいと思いました。」 ピーター・バラカン氏(ブロードキャスター) 「英語を外堀から埋めて、英語へのより深い興味をかき立ててくれる一冊。早期教育に関する考察などは両手を挙げて賛成したい!」 戸田奈津子氏(映画字幕翻訳家) 「これほど豊かな学識に裏づけられた英語論を私は読んだことがない。英語に対する日本人の盲信を打破してくれる名著である。」 斎藤兆史氏(東京大学大学院教育学研究科教授)
目次
プロローグ
第一章 英語という世界語
第二章 英語といかにつきあうべきか
第三章 早期教育と英語の実用
第四章 英語と第二外国語
第五章 英語とフランス語
第六章 英語の中の外国語
第七章 英語の発音について
第八章 コンプレックスをなくそう
第九章 言葉と言葉の相性について
エピローグ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
歩月るな
8
「文章語」はダテや酔狂でこしらえたものではありません。もったいぶって難しい言葉を使い、偉そうな顔をするためにつくったのではない。(頁46)の辺りで妙に慰められました。内容はと言えば、軽い気持ちで読める本。英語圏の訳書ばかり読んでいるが、その他の言語に対してどのように取り組まれてきたのか、歴史的な背景から優しく語りかけてくれるお蔭で、色々な本の会話や舞台背景がさらに腑に落ちるようになる。数か国語を操る諸氏には当然な要素も「歯がゆさ」もちょっと理解できる。会話したいんじゃなくて読みたいから学ぶ、でも良かろう。2018/06/09
pppともろー
6
英語にコンプレックスを持ちがちな日本人。なかなか克服できない。やはり文法は大切。2019/10/05
fumi
5
いわゆる「ビジネス新書」らしいテーマや見出しに、一抹の不安を覚えつつ読み始めたが、南條先生らしい料理の仕方で楽しく読めた。「英語、英語とうるさく言われなくなって初めて英語の魅力に気付きはじめるのでは(要約)」というくだりなど、昨今のトレンドと真っ向から反していて痛快ですらある。氏は語り口こそ派手さはないけれども、こうして読むと博覧強記の人だなあと思う。それとも色々な言語を「かい撫でて」いる人に、私がそのような印象を抱くのかもしれないが。少なくとも氏の小説『酒仙』や他の著書を楽しく読んだ向きにはおすすめ。2018/06/12
Minyole
3
言語にまつわるエッセイという印象です。興味深く読ませていただきました。現代社会ではは、普段英語や英語に似た言語を話している人が圧倒的に有利だよなと常々思っていますが、長い人類史の中では英語が覇権を握った時期はまだまだ短い期間なんだと認識しました。最後の章で、日本人のth、r、lの発音の困難さに触れられていますが、もはやいまさらという感があり、それまでの話が面白かっただけに少し興醒めしたのが残念でした。2018/10/12
wang
2
世界共通言語として使われている英語にまつわる色々な話。後半は他の欧米の言語と違う独特な発展をした英語がいかに特別でどれほど複雑なのか、なぜ日本人に習得が難しいかが語られる。だから完璧に話せないことを深刻に受け止めず、もっと気楽に話せばいいのだと教えてくれる。かなり文法や単語に共通点のある欧米人同士であっても完璧な英語を話しているわけではないのだから。発音記号を使って日本人が区別しにくい発音の違いを説明している部分は特によかった。2023/08/22
-

- 電子書籍
- 俺一人だけカンストレベル帰還者【タテヨ…
-
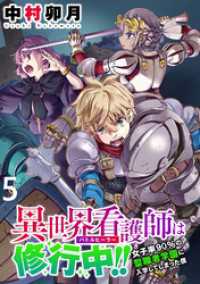
- 電子書籍
- 異世界看護師は修行中!! ~女子率90…