- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
今も昔もお金の貸し借りには、かたちは違うとはいえ一定の秩序が存在していた。だがその一方で600年前の中世社会と現代社会の金融とでは、決定的な違いが存在していたこともまた確かである。その最たるものが徳政である。貸していたお金がなくなるなど、今では詐欺行為と同等かそれ以上の悪辣きわまりない行為だと考える人がほとんどだろう。だが中世社会ではそれが徳政という美々しい名のもとで行われていた。(はじめにより)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
31
分一徳政令を見たときに、徳政令に財政政策的要素(いずれにせよ幕府財政は潤うのね)が付与されたことに言及したが、戦争状況を背景として、今度は徳政令が軍事政策的性格を強める/徳政令は戦争と一体化し、徳政には戦さのにおいがつきまとうことになった。ここにいたり、徳政観の反転は決定的になり、嫌悪の対象/大法の尊重される社会の出現とともに法の濫用も始まっているというお話なのかな。2019/03/11
浅香山三郎
27
『日本経済の歴史 中世』からの流れ。同書の著者執筆部分を分かりやすく説明し、且つ、それが室町時代の社会(都市社会と地域社会)の基本的なあり方をも明らかにすることに繋がつていく。具体例をくどくど書かずに論点をクリアにされることで、原理を述べるコトバが増へて、やや置いてきぼりを喰ふ箇所もあつたが、味読するべき価値がある本である。徳政を糸口にして、社会変動と中世人の観念の変容を明らかにしたこと、近年の政治史と経済史の研究成果の生かし方が絶妙なところなども、示唆に富む。2018/12/21
Kouro-hou
26
学生の頃「徳政令で借金踏み倒すともう貸してもらえないから駄目です」「そうか」と納得したが、その「そうか」の合意が近世日本でいかに形成されたかを近世事情、金融、価値観から語り、またそれを読み解く歴史学史についても語る本。元々は天候不順などの不作による借金を天皇の徳が足りなかった分で徳政だったが、出す方の都合で内容も転々。最後の方は出陣費&給料代わりとか。貸す方も徳政令予測込みで値を上げたりとか徳政利用しません誓約書付き上積みや、預けただけだから!貸してないから!偽装など不便この上ない。徳政令は地獄だぜー!2019/07/06
さとうしん
21
「借金棒引き」の徳政令がなぜ誰からも忌み嫌われるものになったのかを追ったものだが、その議論の過程で、謡曲「自然居士」に見られる法と法のぶつかり合い、室町幕府の幕府法がいかに優位性を獲得していったか、そして頼母子講や親しい人の間での借金など、身近なところで徳政令がいかに人々の信頼関係を破壊したかなど、当時の政治・法・経済・思想・社会生活など、話題が広範に及び、室町時代の総合的な社会経済史としても読めるものになっている。2018/09/03
鯖
20
天災を背景に、幕府の必殺技として生まれた借金帳消し徳政令が室町時代に乱発されたあげく、忌避され、消滅するまでの流れを説いた本。荘園や農村経営からの税収が低下し、莫大な利益をあげていた日明貿易も廃れ、財政基盤が脆弱な足利将軍家は土倉や馬借といった金融業や商業からの税収に依存するようになる。大陸から銭の流入も途絶えたことで、銭の質も落ち、貨幣への信用もなくなっていく。2019/09/15
-

- 電子書籍
- 孤独なソルシエールは恋を紡ぐ 7 マー…
-

- 電子書籍
- FEEL YOUNG 2018年8月号
-
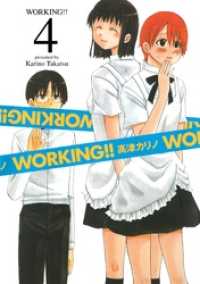
- 電子書籍
- WORKING!! 4巻 ヤングガンガ…
-
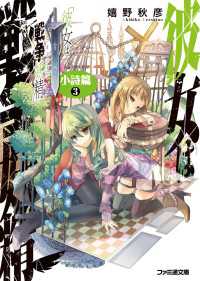
- 電子書籍
- 彼女は戦争妖精 小詩篇 3 ファミ通文庫





