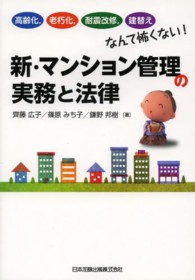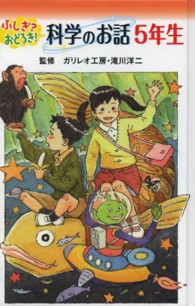- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
これが本当の“神の雫”だ!
古代メソポタミアに造られ始めたワインが、いかにして今日、私たちの食卓に供されるようになったのか。古代エジプトから聖書時代を経て、ローマ帝国におけるキリスト教の布教と共にワインは全世界に広まっていった。ガリア人による樽の発明、中世の「壜・栓・コルクスクリュー」の開発、さらに近世における「発酵」の原理の発見により、ワイン造りは飛躍的な発展を遂げる。
本書は、ワインの歴史とその技術革新をたどりつつ、ワインの楽しみ方の精髄に迫ったものだ。
さらに、シャトー・ディケム、シャトー・ラフィット、ロマネ・コンティ、モンラッシュ、コート・ロティなど、日本ワイン界の重鎮である著書の心を奪った13本のワインをめぐる物語を収録。教養としてのワイン書の決定版!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スプリント
6
ネタ本としてもトリビア本としても中途半端な内容ではありますが入門編としてはよいかもしれません。2018/11/30
Christena
5
うーん。 特に新しい情報なし。著者の偏見や個人的な何かが多少気になった。2018/11/10
Daisuke Oyamada
2
日本は古くから、自分達から排出される糞尿は農作の肥料として利用し、循環システムとして機能していた。衛生面が保たれていることに加えて、日本は水が豊富。飲料水に困ることなどあまりなかった。 かたや、中世のヨーロッパ。 都市に集まった人々は、糞尿は普通にその辺に捨てるし、家畜の管理も不衛生で汚染極まりない社会だった。 そのため安全に飲める水は、ほとんど存在しなかったという。 安全に人体に入れる水分「保存の利く飲用水」として ワインの文化が根付いたの・・・ https://bit.ly/3NJ90W12022/07/04
ソーニャ
2
タイトルの歴史というところにひかれて読んでみた。 前半はタイトル通りで後半は著者が好きなワインについて。帯にあるような本物とか神の雫とかを求め決めていくような本ではない。 フランス革命はワインの世界にも大きな変化をもたらしたことが分かった。壺、壜、圧搾機、樽、コルクなど道具の話も面白かった。後半はワイン世界の幅の広さ、奥深さ、差の細やかさを知れた。2018/12/09
さと
1
フランスを中心としたワインの歴史。昔のワインは水のように薄かったし、甘口が主流でタンニン豊富なものは好まれなかった。まるで自分がワインを覚えた歴史をたどっているようだ(笑)。 後半は、銘醸地のワイン特集のような感じになっている。ペトリュス飲んでみたいなぁ。2018/12/30
-

- 電子書籍
- 仕えたお嬢様がお坊ちゃまになった 第9…