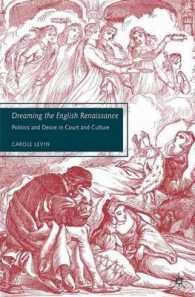内容説明
植民地朝鮮で過ごす幼少期が「僕」の昭和の始まり。受験失敗、厳しい陸軍の日々、敗戦、生活困難のなか書かれた文壇デビュー作「ガラスの靴」。芥川賞受賞の頃には復興も進み時代が大きく変わり始める。六〇年安保の年、アメリカ南部留学は敗戦国日本の戦後の意味を考える視座をもたらした。そして高度経済成長や学園紛争といった新たな変化。激動の昭和を個人的な実感に基く把握と冷静な筆致で綴った記念碑的名作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
68
ものすごく良い仕事をしてくださっていたのだなぁ、と読み始めてすぐ思った。軽妙な文章のなかに、戦争期に自己形成をしなければならなかったご自身の思いを詰め込んでいる。戦中戦後にかけ、戦争に対してシラケたりぽっかりと穴が開いたような気分を持て余していたような描写はフィクションと思えない。このような時代だったのだろうと深く納得した。戦前と戦後、また日本とアメリカの比較文化論的な意味合いもあり、この時代に興味がある方なら必読の文献ではないかと思われる。読み物としてもとても面白かった。2018/11/09
geromichi
5
800ページある本ですが、苦もなく読み進めました。大江健三郎みたいに文学観や読書遍歴を中心に過去を振り返るのではなく、もっと世俗的な出来事と絡めながら、自身の家族や仲間との思い出を語っています。そこが物足りないような、らしくて面白いような。そういえば大江健三郎は全く出てこないけれど、三島由紀夫はやたら出てきたな。2023/10/21
たぴ
1
800ページ近い大著。一人称の安岡章太郎「僕」の目を通して、一つの激動の時代を体験する。そこに映るのは、大きな出来事に共振する「僕」ではなく、具体的なディティールに根ざした彼自身の「別世界」であり、おかしなアイロニーであり、優しくナンセンスなユーモアであった。戦後の太宰評や文化革命期の三島評などは、その冷静な洞察眼が光る一方で、なんだかカッコいい吉行淳之介や、狂気を笑いに包み隠した遠藤周作とのやりとりは、読んでいて微笑ましかった。2020/08/14