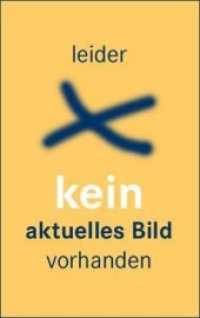内容説明
関ヶ原合戦の記憶も遠のいた1637年、彼らは突如として蜂起した。幕府や各地大名を震撼させ、12万人の大軍をもってようやく鎮められた大規模な一揆は、なぜ、いかにして起こったのか? 「抵抗」や「殉教」の論理だけでは説明できない核心は何か。信者のみならぬ民衆、戦国あがりの牢人、再改宗者らが絡み合う実相を、宗教という視点から戦国時代を考察してきた第一人者が描く。島原の乱を知る必読の決定版!
目次
民衆を動かす宗教―序にかえて
第一章 立ち帰るキリシタン
第二章 宗教一揆の実像
第三章 蜂起への道程
第四章 一揆と城方との抗争
第五章 原城籠城
第六章 一揆と信仰とつながり
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
at-sushi@進め進め魂ごと
58
郷土史勉強中。前に読んだ別の本では一揆的な意味合いが強いとされた「島原・天草の乱」だが、宗教史の観点から紐解くこちらでは、宗教戦争であったという見解。自分達に味方しない村まで異教徒として蹂躙したのは確かに一揆とは違うよなぁ。四郎の手による籠城勢への檄文など完全にカルト教団みたいな内容だし、結構ヤバい奴だったのではなかろうかw なお、天草四郎といえば未だに「魔界転生」の沢田研二の強烈なイメージが頭から離れないワイであった。 2021/11/18
樋口佳之
31
戦国の民衆が支配者をみる目はきわめてシビアであり、「百姓は草の靡き」という諺の通り、弱体な大名や武士は見放され、寝返られ、惨めな滅亡を迎える運命にあった。/戦国時代の民衆が大名の道徳説法に簡単に服するわけがない。近年藤木久志氏をはじめとして、戦国大名といえども「徳政」を行い、領国の治安を保って民衆の支持をとりつけることが必要であり、さもなければ存立基盤を失うという、民衆の思惑に規定された存在であったことが指摘されている/島原の乱をケースにした戦国近世宗教論と読みました2019/03/15
高橋 橘苑
22
ひっそりと読メ再開します。さて、本書を手に取った軽い動機は、島原の乱の経緯と天草四郎という人物に興味を持ったからである。残念ながら、天草四郎に関しては史料の少ない人物らしく、その人となりに触れる箇所は多くなかったが、島原の乱のあらましは知ることができた。注目すべき点は、一揆の圧倒的多数が一旦迫害に屈して棄教した「立ち帰りキリシタン」であること、著者の推論として、苛政と飢饉による絶望がキリスト教的終末思想に火を点けてしまったということであろうか。いつの時代も、現在の重さが過去への逃避につながるのだろうか。2020/05/07
穀雨
11
宗教史の研究者が島原の乱の全体像に迫った元新書本。同時代史料を博捜した上で随所に引用している点が特徴的といえるが、たぶんにキリスト教的バイアスがかかっていると思われるイエズス会年報まであちこちで無批判に引用している点にはすこし引っかかりを覚えた(史料が少ないという根本的な事情もあるだろうが)。また、一面の焼け野原、無人地帯となった戦後の島原・天草地域がどう復興を果たしたかという点に興味があったので、そこにも触れてもらえるとありがたかった。2022/09/27
MUNEKAZ
10
もとは2005年に中公新書で出たもの。島原の乱について、「立ち帰りキリシタン」が主体の実情や終末思想の流行、神社・仏閣の破壊を根拠に宗教的な蜂起と位置付ける。松倉家の苛政や飢饉は副次的な要素とし、著者の持論である「天道思想」と絡めながら乱の原因を探っている。面白いのは一揆に参加する浪人の存在や、戦場に動員される「百姓」など戦国以来の部分が色濃く残る点。戦国と太平の狭間に起きた乱だということが強く印象に残った。あとがきで原書に寄せられた批判にも答えており、こちらも興味深い。2018/08/25