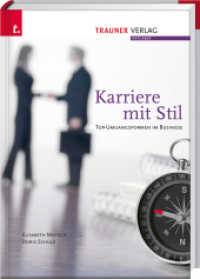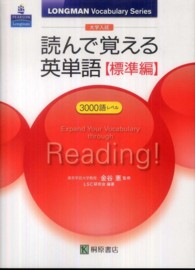内容説明
正規労働者であることが要件の,現在の日本型雇用システム.その不合理と綻びはもはや覆うべくもない.正規,非正規の別をこえ,合意形成の礎をいかに築き直すか.問われているのは民主主義の本分だ.独自の労働政策論で注目される著者が,混迷する雇用論議に一石を投じる.
目次
目 次
はじめに
序 章 問題の根源はどこにあるか──日本型雇用システムを考える
1 日本型雇用システムの本質──雇用契約の性質
2 日本の労務管理の特徴
3 日本型雇用システムの外側と周辺領域
第1章 働きすぎの正社員にワークライフバランスを
1 「名ばかり管理職」はなぜいけないのか?
■コラム■組合員資格と管理職
2 ホワイトカラーエグゼンプションの虚構と真実
■コラム■月給制と時給制
3 いのちと健康を守る労働時間規制へ
4 生活と両立できる労働時間を
■コラム■ワークシェアリングとは何をすることか?
5 解雇規制は何のためにあるのか?
第2章 非正規労働者の本当の問題は何か?
1 偽装請負は本当にいけないのか?
2 労働力需給システムの再構成
■コラム■日雇い派遣事業は本当にいけないのか?
3 日本の派遣労働法制の問題点
4 偽装有期労働にこそ問題がある
5 均衡処遇がつくる本当の多様就業社会
■コラム■職能資格制度と男女賃金差別
第3章 賃金と社会保障のベストミックス──働くことが得になる社会へ
1 ワーキングプアの「発見」
2 生活給制度のメリットとデメリット
■コラム■家族手当の社会的文脈
3 年齢に基づく雇用システム
4 職業教育訓練システムの再構築
■コラム■教育は消費か投資か?
5 教育費や住宅費を社会的に支える仕組み
■コラム■シングルマザーを支えた児童扶養手当とその奇妙な改革
6 雇用保険と生活保護のはざま
■コラム■登録型プレミアムの可能性
第4章 職場からの産業民主主義の再構築
1 集団的合意形成の重要性
2 就業規則法制をめぐるねじれ
3 職場の労働者代表組織をどう再構築するか
■コラム■労働ngoとしてのコミュニティユニオン
4 新たな労使協議制に向けて
■コラム■フレクシキュリティの表と裏
5 ステークホルダー民主主義の確立
参 考 書