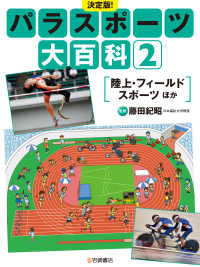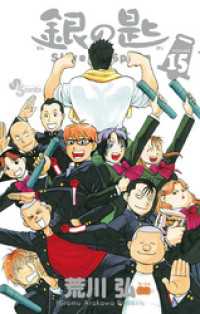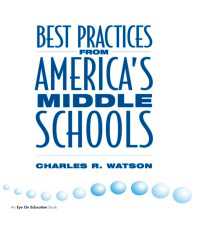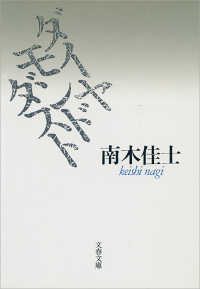内容説明
学習上・生活上の困難を抱える子どもの問題行動、不登校、場面緘黙、情動コントロール、極端な思考の偏りなどに有効な手法を事例や漫画とともに解説。「やりたくない」「できない」の原因を見つけ、自己選択と自己決定で成功体験を積ませて自尊感情を育てる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おやつ
11
こういうことかぁ!<やる、100><やらない、0>の2択ではなく、10,20,30,40・・というように段階を区切って提案し、どこからならできるかを相手に選択させる。よりきめ細かな支援の形だと感じました。叱らないけど譲らない、とありますが、叱らない、諦めない支援というほうがしっくりくるかもしれません。2019/04/02
erie
7
これを現場の教員たちが書いているというのだから驚きである。これだけの深い理解と適切な姿勢を持った教員が、かくもたくさん活躍している和歌山では、どういった教員養成がされているのか。ジェンダー比も多様性がある。しかし支援者を得られず大人になってしまった身としては、書かれている定型発達者の思考が理解できないものも多々あり、指導や矯正や褒賞を自力で供給するに限界が大きい。せめて次世代の子供が少しでも幸せに生きられるよう祈るばかりか。2019/06/23
じゃがたろう
6
白黒思考が強い人にかかわるときにはいろんな選択肢があるということを伝えてあげるだけでも助けになるのではと思う。和歌山県の特別支援教育の素晴らしさも感じる。9事例の実践が書かれているが、信頼関係という前提条件があることを忘れてはならない。譲れない部分を明確にして、できる限りの可能性を提案していく。理想的。2019/08/14
桜井和寿
5
子どもの自尊感情を上げるために大切なことだと思う。「寄り添う」とか「毅然とした態度」とか、大切なことは頭ではわかってる。それでも教師として困るときは沢山ある。子どもが自分のモヤモヤした気持ちに気づくこと、その上でどうしたらうまい道を進むことができるのかを提案すること。子どもが「やらない」を選択したとしても、大人の単なる放任(お手上げ)とは違う意味を持つというマインド。「経験がものを言う」とでも言いたくなるような子どもとのやりとりについて書かれたとても実践的で実用的な本だと思う。 本の最初と最後が特に大切。2018/10/06
Totsuka Yoshihide
4
国立特別支援教育総合研究所で筆者の講義を受講し感銘を受けて購入。甘やかして本人の好きなままにするのではない。怒ったり叱って指導するのでもない。でも本人の想いに寄り添いながら譲らないという考え方がとても印象に残っている。提案・交渉型アプローチはぜひ若い先生方に伝えていきたいと思いました。2025/02/16