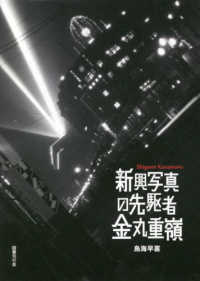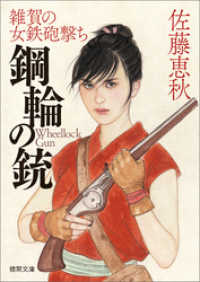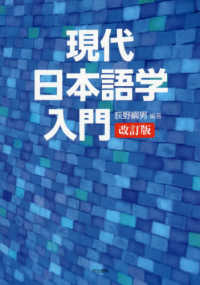- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
なぜ人間だけが言葉で話すようになったのか? 言語はコミュニケーションの手段ではなく、世界を俯瞰する眼としての自己を産み出した。人間のあらゆる認識、思考、行為の根幹をなす言語という現象の本質に迫るスリリングな論考。言語は内面に向かい、孤独は人を結びつける。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
29
「群像」の連載をまとめた、評論家による哲学書。大岡信、司馬遼太郎、折口信夫、小林秀雄、夏目漱石‥‥過去の評論や小説、詩歌を題材にして、思考の海を縦横無尽に渡っていく。宗教は詐欺である。支配とは人間を飼いならすシステムである。人は自分を騙しながら生きてゆくほか生きようがない‥‥。脳みそに汗をかく笑、難解度ですが、所々に首肯する解釈や箴言もあります。個人的には10〜12章が比較的読みやすかった。2019/05/06
かめぴ
12
思ってた内容と違った…孤独は言語の別名、孤独は言語と共に古い。何だそれ、からのでも何となく言いたい事は分かる、で読み進む。国語とは何か、アポリアは言語の所産、英語は国語ではなくクレオールに過ぎない…まさにチャゲアスの「言葉は心を超えない〜」ではないか!と驚き、紫式部、夏目漱石から有名どころの哲学者、宗教家の書評かと気づき、孤独とは自己欺瞞に共感して、最後、私の本を読んでくれる読者は少ない…にもっと共感して吹く。読者、少ないんだろうか。2018/12/16
gorgeanalogue
4
言語は音声コミュニケーションの結果生まれたのではなく、徹底して視覚的なものとして「世界を俯瞰する眼」としての自己を生み出した、というのは素直に納得できる。チョムスキー、リルケ、井筒俊彦……。さまざまに飛躍しながら繰り返しテーマが変奏される。ただ後半、「騙し/騙される」「集団/社交」などのキーワードはあんまり説得的でなく、また全体的にもその長さにかかわらず、なんとなく底が浅い。中途半端に思弁的になろうとせずに、「文学論」としてコンパクトに改めて書き直したほうがいいのでは。2019/01/14
袖崎いたる
4
三浦雅氏がなぜ岸田秀と仲がいいのかわかる。唯幻論者のひとりと言っていい。読書歴が浅いとたぶんどっぷりハマるタイプの著者だと思われるので、ご注意を。2018/11/26
takao
2
ふむ2020/03/20