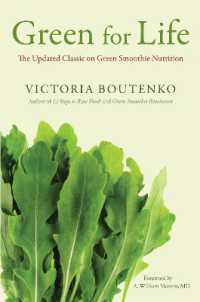- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
声とは教養そのものである。声に気づけば、人間関係が潤う。私たちは話す内容より「声」で判断される──舞台演出家かつ「非言語情報」の専門家が、究極の自己財産である声の活用法について、テクニカルとメンタルな面の双方から迫る。超実用的人生読本。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
58
そうは言っても、持って生まれた声質は変えられるものではないと思うのだが……。内容的に、喋り方や話し方、せいぜい発声のときに気を付けましょう、と言ったところか。主観的な余談の部分が一部不愉快だった。2018/07/16
としP
18
声が印象を大きく左右するというのは、実感としてよく知っていた。この本からはそれ以上のことは特に得られなかった。2019/02/22
べる
17
自分の声を「創る」ことが大事。自分の声は変えられる。声はそもそも相手に伝えるために生まれた。伝えたい気持ちがあることが最も大切。音量、速度、抑揚、流暢さ、間、人間的魅力。文学作品の朗読CDは俳優の技、声そのものの質を堪能できる。首や肩の凝りは良い声を出せない。人は音を身体全体で聞く。朗読サークルや教室はブーム。言葉はもともと音声で生まれたから朗読によって頭だけで理解していたことが身体でわかる。恥ずかしい気持ちを捨てて自分以外の存在になるのは快感。人は自分の求める声をBGMにしたいもの。イメージの源は知識。2022/03/05
ふたば
7
自分の声が嫌いだ。薄っぺらくて、鼻にかかった、もったりした声なのだ。中学生の頃からのコンプレックスなのだ。 今の時代、声はコミュニケーションツールにはなりにくい。しかし、ノンバーバル言語を含む言語によるコミュニケーションは人間である以上は避けて通ることのできないもののはずである。 何か伝えたいことがあるから言葉にする。伝えようという意思があるから言葉には力が宿る。美しい声、個性的な声、誰かの心に訴える話し方をしたいと思う。少し訓練しよう。誰かに響く話し方のために。2019/06/01
sho watabe
6
発声方法なども記載はあるが、内容的にはもっと根本的な話。 「はじめに」で書かれている次の文章が印象的。 ・「声」にまで意識が届いている人は、本来の意味で「頭がいい」。 確かに普段から声を意識して喋っている人は少ないと思う。 しかし、人間は文字が発明される前から声を使ってコミュニケーションをとってきた。 なので、本能的に声でその人の情報を読み取る能力が備わっていると思う。 それを利用して、自分の声をちゃんと演出できる人は確かに頭がいい人なのかもしれない。2020/02/22
-
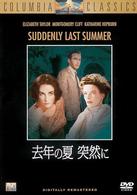
- DVD
- 去年の夏 突然に