内容説明
ちまたを騒がせるヒアリ、夏の風物詩スズメバチとアシナガバチ、刺されたら最も痛いサシハリアリ……お馴染みの面々から、外国の恐ろしいハチ・アリまで実際に刺されたシュミット博士。
その痛みを毒液や生態と関連させるというユニークな手法で、刺されると一番痛い昆虫、痛みの原因となる物質、ハチ・アリ類の防衛戦略と社会性の発達……素朴なギモンから深遠な進化の歴史まで、ハチとアリの知られざる一面を明かしていきます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
54
読みはじめて笑いが止まらず、こっちが死ぬところだった。思い出すのは日本の有名なスズメバチ研究家であった松浦先生。先生も幼き頃の痛い思い出が研究のきっかけになったが、しかしこの人の研究+学生のうわあ!なデータ収集はもうイグ・ノーベル賞を受賞したことであまりにも有名だが…もうこの変態的偏愛がもう素敵すぎて、読みはじめたら止まらなかった。アリの仲間のデータが充実しているのが素晴らしいところだけれど、アメリカ大陸に集中しており、オオスズメバチの指数がないのが残念でした。2019/05/01
けぴ
50
著者は虫刺されの痛みスケールを作った功績で2015年にイグ・ノーベル賞を受賞した。訳者あとがきに本書のポイントがまとまっている。強烈な痛みを伴うのは防御用に使われる毒針だということ。そして、集団として守るべきものをたくさん抱えている種ほど、その刺針は痛く、毒液の毒性も高い。刺針を装備していて相手を刺すことができるのはメスだけ。刺針は産卵管から進化したものだからだ。メスは交尾を終えたあと、体内に精子を蓄えておけるので、小出しにしながらずっとその精子を使い続ける。受精卵からメスが、未受精卵からオスが生まれる。2022/12/11
真香@ゆるゆるペース
38
図書館本。タイトル通り、昆虫学者の著者が体を張って蜂と蟻に刺されてみたり、食したりして、その研究結果をまとめた本。結果だけでなく、刺した昆虫の生態、毒針の意義、痛みの正体などの話も素人でもとっつきやすいようエッセイ風に丁寧に解説されていて、読み物として非常に面白かった。巻末の付録で「毒針をもつ昆虫に刺されたときの痛さ一覧」として、これまでの刺された記録が分かるように記されており、何と100種類以上の蜂と蟻に1000回以上(!)刺されてきたのだとか… 著者の旺盛な好奇心と貪欲な探求心に、ただただ脱帽。2019/02/15
トムトム
32
虫刺されの痛みをスケール化してイグノーベル賞をとった著者さん。ありとあらゆる蟻・蜂に刺されています。こういう人、好きです♪生態の説明から痛みの表現まで、面白い本でした。2021/10/18
更紗蝦
30
原題は『THE STING OF THE WILD』(自然界における毒針)で、「虫刺されの痛さ」のみを追究した本ではなく、刺針を持つ昆虫(蟻と蜂)の進化、生態、人間との関係(共生と対立)について論じている本です。特に面白かったのは進化に関する部分で、「社会性がある(コロニーを形成する)種か/単独性の種か」の違いが「痛さ」と「毒性」の強さに深く関わっているという話が印象深かったです。2019/04/10
-

- 電子書籍
- 【分冊版】はだしのゆずりはちゃん(21)
-
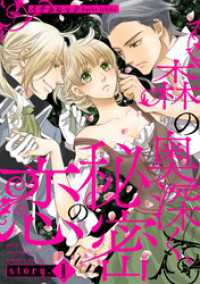
- 電子書籍
- 森の奥深く、秘密の恋【単話版】 sto…
-

- 電子書籍
- 王子と孤独なシンデレラ【分冊】 10巻…
-
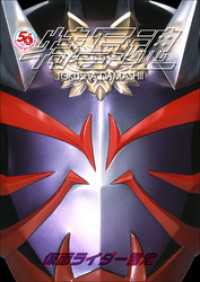
- 電子書籍
- 仮面ライダー特写魂 仮面ライダー響鬼 …
-
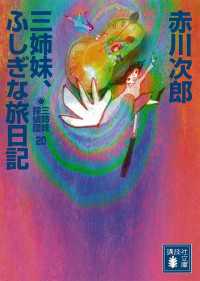
- 電子書籍
- 三姉妹探偵団(20) 三姉妹、ふしぎな…




