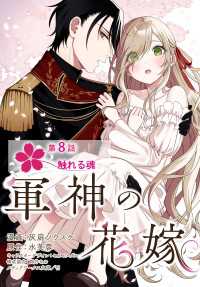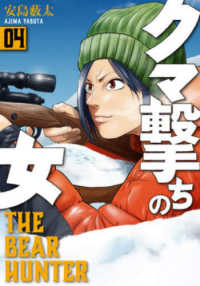内容説明
なぜ京都・綾部市は限界集落を再生・元気にしているのか? 本書には地方創生の秘訣やヒントが満載!
*「(活性化は)いまさらもう無理」「なにをやってもダメ」とあきらめていたおばあちゃんたちが「これまででいちばん幸せ」と俄然元気になった理由は?*荒れ果てた杉林を間伐したら、400万株のシャガの花を発見! 毎年一万人が来る一大観光スポットに!*地元の小さな山に手を入れることで、週末トレッキングで注目!*自分たちが忘れていたものが、集落外で思わぬ評判に。右肩上がりに販売数を伸ばす「瀬尾谷粕漬」等々
本書はこういった、限界集落を水源の里に呼び換えて「再生」を図っている、京都府綾部市の16集落の事例を紹介しています。そして「水源の里」という考え方は全国へと広がり、「全国水源の里連絡協議会」が生まれ、現在全国161の市町村が参加しています。綾部以外の取り組みも最終章で紹介しています。集落再生、まちづくりのヒントになるだけでなく、暮らしやビジネスヒントにもなるものでしょう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
33
最も驚かされたのは、瀬尾谷(しょうだに)集落では、高齢化率9割でも、地域資源である黒瓜を使った粕漬を農産加工品として製造していることだ。もしかすると、65歳以上のお年寄りが100%であったとしても、集落で働きながら生き甲斐を感じられる人生を謳歌できるのかもしれない。多くの限界集落への誤解をなくすには水源の里から学べることなのだと思う。2019/05/04
アナクマ
28
綾部市の取組みを中心に。地区それぞれが蔵する魅力をカラー写真とともに伝え、色々あるな!と思わせる。ちょっと断片的ですが。◉わが町にはあれが無いしここも違うから、とマイナスを数えるのは読み方が間違っている。あの人たち面白そうなことをやってるな〜は、長期的には必ず正の影響を及ぼすと考え、応援・実践あるのみ。◉とはいえ、市中のお宝は個人の熱意努力だけでは萎んで埋もれがち。注目したかったのは行政側の支援と苦労とルール運用。しかし、そこは別の資料にあたった方が良さそうです。行ってみるのが一番か。2019/01/12
hiyu
8
当初は横石 知二氏の「そうだ、葉っぱを売ろう!」のような内容かと思っていた。個人的に細かいところで気になる部分はいくつかある。例えば、どうしてプラスの面だけ示しているのか、もう少し深く掘り下げることも方法としてあったのではないか等。何よりも本書中の「シュンとしていた地域に誇りと自信を取り戻す」が響いた。ついつい結果を出そうとするあまり周囲を見れていなかった自分には相当感じるものがあった。2018/07/31
くま
4
何か事業を起こすとき名前はとても大切で、「水源の里」という名がとてもすてきだなと思いました。この本を読んでふと思いついたことが。若者は刺激のある都会へ出たがる。これは仕方がない。でも、彼らが食べるものは、吸う空気は、飲む水はどこから生まれるのか?日本は少子高齢化の影響で人口が減りますが、世界人口はまだまだ増えます。しかも、現在の発展途上国が経済的な力をつけ、アメリカ並みの生活をしようとするれば必ず食糧不足は怒ります。だから、食糧生産の地方と都市を結ぶ、しかも小規模で。そんな仕事をしてみたくなりました。2018/11/11
猿田康二
3
国の考える「コンパクトシティ構想」に反して、あやべ市が制定した「水源の里条例」を通して「限界集落」が奇跡の復活を遂げる、及びその過程を著者がそこに住む人に寄り添って伝える渾身のレポート。そこには日本全国の田舎が抱える「少子高齢化」という現実を受け入れつつ且つ生き残るためのヒントが詰まっており、読んでいてこんな方法もあるのかと、何度も膝を打った。地方創生は、国が変に口を出すのではなく、それぞれの自治体に任せることが必要だと改めて確信した。2018/11/17