内容説明
紫陽花を愛し、鎌倉雪ノ下に永く暮らした近代日本を代表する日本画家、鏑木清方は、名随筆家でもあった。挿絵画家の父の影響で若いころから文藝に親しみ、泉鏡花とも親交があり、多くの随筆集を残した。失われた市井の人々の暮らしへの尽きることのない愛惜、清方の晩年の折々の記、その源泉を辿る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
65
天は二物を与えず、とはいうものの著者のように画才と文才を兼ね備えた人もいる。というわけで著者の随筆を読んでいると過ぎし日の追憶と豊かな自然に陶然とする思いがするのです。本書は主に戦後から鎌倉に移住した時期の作品が中心としてまとめられている。そのため先に読んだ岩波文庫とは違い、時事問題や人間関係に触れたものも多く収録されている。ただやはり著者の本領が発揮されたのは、足元にある自然や遠い江戸明治の世に触れた部分だと思う。個人的には上村松園関連も興味深かったが。とあれ読んでいると静謐な気分に慣れそうな一冊です。2025/01/05
belle
9
講談社文芸文庫から、鏑木清方の随筆集が出た。画家の作品で最も多く目にしているのは、「野崎村」。お染の愛らしい姿が国立大劇場の2階の壁を飾っているから。観劇の度に会いに行く。ゆるゆると心に沁み込む美しい絵と同じように、清方の文章は水の如く読者の心を満たす。角は立っていないけれど知的で的確。根っこには文人の血が流れる。日々の暮らし。鏡花や松園のこと。自らの画業。ゆっくり味わって読了。紫陽花の季節はとうに去ったが、この本は手元に。2018/11/13
salvia
8
鏑木清方による1946〜1969年の随筆を編んだもの。絵は幾度も見ているが文章を読むのは初めて。日本画家らしく映像が浮かんでくるような文章で「季節への郷愁」を誘い、上村松園論や円朝との思い出話では人物を描くのも鮮やか。「風待」「秋水」などの風物詩的な美しい言葉を知った。2020/11/19
Mana
4
12月に近代美術館で築地明石町の展示を見に行ってきた縁で手にとった一冊。読みやすく人となりの伝わる文章だった。本書の中でも築地明石町の話は何回か出てくるけど、晩年に再開した時の感慨は胸にくる。画家も手放してしまうとなかなか自作と再開する機会はなくなるんだな。展覧会で44年ぶりと言ってたけど、この時点でも築地明石町の三部作の所在は注目を浴びてたらしい。こうして美術館で見せてもらえるのは嬉しいけど、好事家が大切に秘蔵してたからこそというのは難しい。2020/01/10
ゆかっぴ
3
以前に新聞の書評で知った一冊。戦争の時代を生きた画家の生活や、泉鏡花や上村松園との交流など興味深く読みました。さらりと書かれていて読みやすい中に凛とした佇まいが感じられます。2019/07/27
-
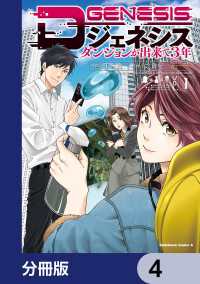
- 電子書籍
- Dジェネシス ダンジョンが出来て3年【…
-
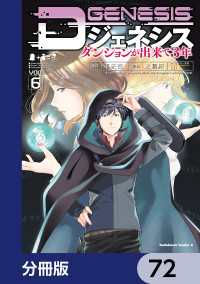
- 電子書籍
- Dジェネシス ダンジョンが出来て3年【…
-
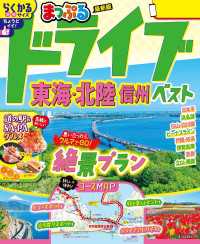
- 電子書籍
- まっぷる ドライブ 東海・北陸 ベスト…
-

- 電子書籍
- ギルドの受付魔人~無限チュートリアルで…
-
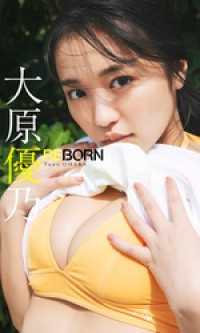
- 電子書籍
- 【デジタル限定】大原優乃写真集「REB…




