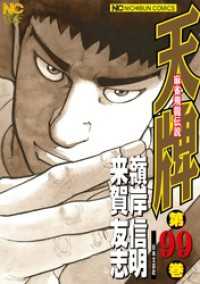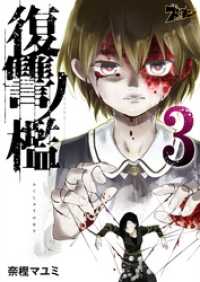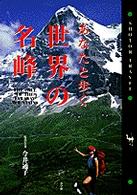内容説明
日本は、つねに中国を意識してきた。とくに、明治維新以後、中国研究はきわめて深く、幅広いものとなり、東洋史という歴史分野を生み出した。「日本人の中国観」の形成と変遷を跡づけると同時に、日中関係を考え直す契機となるのが本書である。石橋湛山の「小日本主義」とはなんだったのか。巨人・内藤湖南の「唐宋変革論」とは? 宮崎市定や谷川道雄など、数多くの論者の中国論にふれ、その歴史を読み直す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
26
近代日本の言論人・知識人は、中国をどのように見てきたのか。本書では主に石橋湛山、矢野仁一、内藤湖南、橘樸、谷川道雄らの著述を紐解きながら戦前・戦中・戦後の時代背景も合わせて考察している。とりわけ参考になったのは「唐宋変革」(唐代までを貴族支配の[中世]宋代以降は平民が勃興した[近世]と捉える学説)をめぐる学会内部での論争とその影響、及び東洋史学の成り立ちについての解説。◆時代区分に関する論争や中国社会の「共同体」の概念に関する論争なども、学問上どこまで西洋モデルを適用させるかが問題の本質のようだ。2018/08/27
さとうしん
17
戦前・戦後の主に東洋史学者による中国観や議論を追う。明清をつきつめて研究しなかった内藤湖南と明清を専門とした矢野仁一との対比、時代区分論争で対立しているようで共通の議論の土台に乗っていた歴研派と京都学派の宮崎市定の話など、話題の詰め込みようを見ると、戦前・戦中編と戦後編で分冊した方が良かったようにも思う。「中国という対象は、きわめて難解」と言うが、アメリカや西欧、インドなど他地域を対象とするより難解なのだろうか?いずれにせよ問題なのは、むすびのタイトルにあるように「日本人のまなざし」なのだろうが…2018/07/18
かんがく
15
明治〜現代にかけてのジャーナリズムや研究者が、中国をどのように捉えてきたかという通史。近くて遠い近代中国についての様々な学説は、現代中国を捉える上でも有用なものである。2019/07/14
Kai Kajitani
15
この本は戦後日本の「進歩派」から「リベラル」に至る政治的立場の脆弱さを、その「中国観」の不在に求めるものとして読むことができる。典型的なのが石橋湛山である。戦前の石橋は中国を大して知らなかったがゆえにそのナショナリズムを日本と同一視した小日本主義を唱え、戦後の平和主義のアイコンとなりえた。対照的なのが中国を「知りすぎていた」がゆえに日本の大陸侵略にコミットした矢野仁一だ。しかし、中国の影響力が拡大した現在、湛山的な中国と日本を同一視するリベラリズムは果たして有効か。本書はそう問いかけているように思える。2018/08/18
ピオリーヌ
14
今まで漠然としか知らなかった時代区分論争が詳しく解説され、大変勉強になった。34歳の若さで亡くなった前田尚典「東アジアに於ける古代の終末」が大きな影響を与えたとは。また必読の文献として岸本美緒『地域社会論再考 明清史論集2』島田虔次「序論」『アジア歴史研究入門 1 中国Ⅰ』島田虔次『中国の伝統思想』吉川幸次郎『支那人の古典とその生活』が挙げられる。谷川道雄『隋唐帝国形成史論』も挙げられるが、この本、最寄りの図書館にあってもう十数年も気になっているのだが未だ未読。そろそろ読みたいところ。2023/08/26