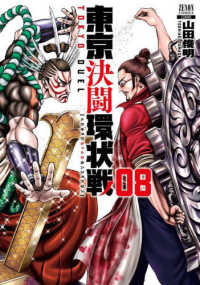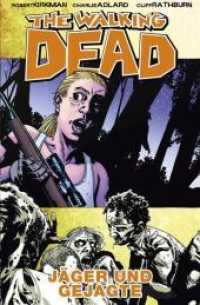- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
「電動化」「自動化」「コネクテッド化」の強化をめざして,いま世界各国の自動車メーカーが次世代のクルマの開発にしのぎを削っている.その技術的進化には,自動車産業のビジネスモデルのみならず,私たちの生活をも大きく変えてしまうほどのインパクトがあるとされる.何が変わるのか.開発の最前線に迫る.
目次
目 次
プロローグ
第1章 クルマがこのままでは立ち行かない理由
第2章 すべてのクルマはevになるのか
第3章 ドライバーのいらないクルマはいかにして可能になったか
第4章 自動車産業の未来
エピローグ──サービス化はもう始まっている
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hatayan
54
「電動化」「自動化」「コネクテッド化」という自動車業界を取り巻く大きな変化に対応するには機敏さと柔軟性を採り入れることが必要と力説。日本の土俵で勝負できないと悟った世界の関心はハイブリッドではなく一足飛びに電気自動車に向かっており、過去の携帯電話や液晶のように成功事例にこだわると日本だけが変化に取り残される恐れがあるとも警告します。自動運転が普及すると携帯のアプリを通してクルマをサービスとして利用する「MaaS」が身近になると予想。近未来で起きることを一般の読者にわかりやすく伝える入門書として最適です。2020/10/05
樋口佳之
24
EV化とサービス化についてはなるほどとも思い電機総崩れの後残る一本柱としての自動車産業の近未来をあれこれ想像する事ができる内容でした。/運転手のいない自動車については夢想だろうと。軌道を走る鉄道や障害が無い飛行機でも実用化されてないのだから。事故が起こった場合、運転手が不在というその状態を受け入れる事が出来無いと思います。2018/07/19
koji
19
日経BP出身技術ジャーナリストが書いた岩波新書。電動化、自動化、コネクテッド化に分けて、丁寧に要領よく纏められており、知識の整理に役立ちました。では、膨大な日本の下請け中小企業群はどこを目指すべきか?難問です。2018/07/27
やすほ
12
【☆☆☆☆☆】 「電気自動車って良く話題になるけど、結局のところ普及しないのでは」と言うのが一般的な感覚だと思う。話は変わるが、ブラウン管テレビよりも性能でもコストでも劣っていた液晶が普及したのは何故か。一番の理由は多くの企業が液晶を選び、多くの投資がなされ、それにより部材のコストが下がり、技術の進化が起きたため。欠点の多い技術も主流になってしまうと不可能を可能にする技術革新が起きる。今、電気自動車はこの状況にあると言う。自動運転の話もサービス化の話も非常に興味深く、これからの20年間の車の進化が楽しみ。2019/03/21
kenitirokikuti
11
著者は日経BP出身の(クルマ系)技術ジャーナリスト。著作は運転するクルマ評論家タイプではなく、本書は産業寄りの内容▲前半。なぜEVAがなのか。従来の内燃機関自動車メーカーがEVにシフトする理由のひとつは、トヨタのハイブリッド車が参入しづらい領域であるため。EVにも欠点は多いが、利点も多い。著者は燃料電池車には否定的▲後半。「自動化」。これはロボットの領域。SFではロボやメカがそこらを歩いてるが、現実には案山子ばかりである。ロボットなら充電池式が当然。2018/05/30
-
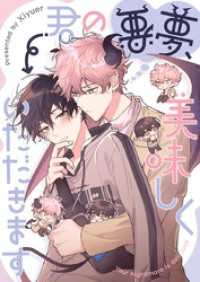
- 電子書籍
- 君の悪夢、美味しくいただきます【タテヨ…