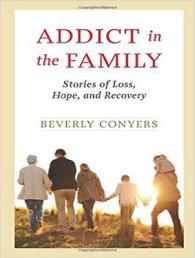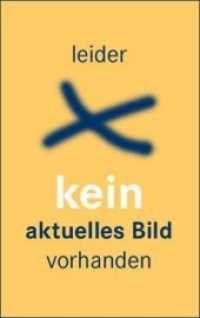内容説明
前著『花びら供養』に続くエッセイ集第二弾にして追悼の書。『全集』未収録の文章のほか、インタビュー、対談、書評を収集。
タイトルの「綾蝶」とは、著者が引用する「東(あがり)うちむかて飛びゆる綾蝶(あやはびら)」という球歌の歌いだしからとったもの。「あやはびら」とは「魂(まぶり)」、「生きまぶり」のことをいうのだとして、孤島の魂であるそれを自らの魂に重ねていた。
石牟礼作品に通底する文字以前の世界との目眩く共振、陽光の中の闇に瞬く言霊の旋律に、今こそ出逢い直したい。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
95
石牟礼道子さんの綴るお言葉は、音読すると懐かしい気持ちになる。小さい頃に日常や遊び、自然の中から受け取っていた一種のリズムと身体と心いっぱいに広がる音楽性があるからだ。石牟礼さんのエッセイを収めたこの本では、失われていく音楽的とも言える各地の言葉に対する愛おしさ、苦しんでいる人はまだいるのに冷たく、片付け、目を塞ぐ権力者への憤り、その悲しみ、怒りを抱えながらもそれでも赦す人への敬意に満ちている。その中でも石牟礼さんのお言葉を通して杉本栄子さんへの覚悟と強さに対峙した時は胸いっぱいに熱いものがこみ上げてくる2018/09/19
chanvesa
35
「命というのを物質化して考えれば考えるほど、公害みたいなものはもちろん出てきますし、人間を管理するだけの…だれか管理する者がいて私たちの生活、生存そのものが管理化されてしまうという、そういうことであってはならないという思い(128頁)」石牟礼さんの思いが随所にストレートに現れるこの本で、特にその思いの強さを感じた箇所である。ぽーっとした人を生産不適合者として管理するのではなく「悶え神(144頁)」とする社会、それは遠く過去となり詩的な世界にしか見出だせないのかもしれない。2022/09/26
松本直哉
32
美しい表紙の美しい題名の本。綾蝶(あやはびら)は蝶であると同時に琉球では魂を意味する。ギリシャ神話の魂の表徴であるプシュケが蝶の翅で表現されるのを連想する。綾蝶とはまさに石牟礼自身のことではなかっただろうか。言葉なきもの、言葉を喪ったものの言葉を傾聴し、その魂に憑依する巫女のように、海と陸のあわいの渚の生きもののように、この世ともうひとつの世を自在に往き来する、そのために彼女がつねによりどころとしてきたのは文字に定着される前の言葉、言葉以前の歌、言葉の原初をとどめる方言だった。2020/03/09
ちゃっぴー
17
石牟礼道子さんのエッセイ、講演、対談など。「苦海浄土」は、水俣病患者の苦しみが石牟礼さんに憑依したかのような重さだった。この本で彼女の感性に触れ、腑に落ちた。優しく響く方言、美しい日本語をかみ締めるように読んだ。2020/07/13
algon
11
「苦界浄土」という日本文学にとっては非常に大きな足跡をいきなり残したために作家の事績そのものが日文ファンにとっても親しみづらい作家という妙にユニークな面を持つのだが、作品がとことん不知火海周辺ということ、そして天草方言ということもあるのかもしれない。そしてまた「南島での書簡をとつおいつ眺めてみるのだが憂悶のたゆたいが、ところどころ…」というような手練れの文がどれだけの読者を魅了できるのか…と言う疑問もあるにはある。しかしほぼ初出文を集め、著者の生前に間に合わず逝去後3か月で刊行された本書、興味深く読めた。2024/09/23
-
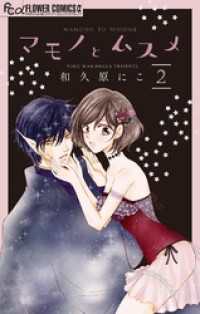
- 電子書籍
- マモノとムスメ【マイクロ】(2) フラ…
-

- 電子書籍
- 大ぼら一代 第1巻