- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
富裕層課税の歴史をたどり、国はいつ、なぜ富裕層に課税するのかを明らかにする。不平等拡大を踏まえた税制議論ための基本研究。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
33
2016年初出。原書タイトルTaxing the Rich。データは入手可(http://press.princeton.edu/titles/10674.html)。 結論として富裕層への課税を望む者は、20世紀ではなく19世紀に主張されたタイプの補償論に目を向けるのがよい。あの時代、所得税を累進的にして、ほかの国税による逆進的な負担を相殺する必要があるという主張が多かった(25頁)。公正さについての考えが、人びとの選好や政府による税政策選択の動機となるか否かに関しては、学問的な取り組みがずっと少ない。2018/10/20
Mc6ρ助
8
公正な負担、支払い能力に応じた負担、政府の不平等な施策への補償、考えられるお金持ち課税の根拠、歴史的には、「体を徴るなら金も徴れ」(p175)という第一次、二次世界大戦の大規模徴兵の補償のみ有効だったとのこと。しかも兵器の進歩により今後大規模徴兵はない・・・。金持課税の道は険しいという著者が基本的に金持に課税すべしと考えていることは伝わってきて、そこは好ましく、その根拠の提示が出来ないことが痛々しい。2018/08/30
人生ゴルディアス
5
富裕層への累進課税の考察という珍しい内容。富裕層への増税はするべきと思いつつ、そこに根拠がない……というもやもやは確かに感じていた。著者たちは増税の根拠を補償論、特に総力戦の戦争に求める(アメリカでさえ80%の税率!)。実際、西洋東洋問わず徴税は武力階級が担ってたし、戦争を前提にしていた物が多い。また、課税を考察する際の、補償論、平等な扱い、支払い能力論という分類も非常に理解の助けになった。良書。仮想通貨ブーム以来、通貨の本質なども含めて、国家とお金の関係は新しい局面に差し掛かっているのかも。2018/08/29
Sumiyuki
5
第1章と第9章のみ読了。財政社会学的分析。租税負担の原則は応益と応能。筆者はそれに補償論を加える。補償論とは、ある税の負担が市民全体で均等ではないなら別の税を使ってバランスを取る考え。所得税の最高税率が最も高かったのは、戦時中と戦後。つまり、金持ちの徴兵逃れに対する補償という意味合い。終戦後、各国の最高税率は軒並み下がった。金持ちへの重税は公正ではないと市民が考えたからだ。著者は、最高税率を上げるよりも、控除や適用除外をなくしたり、今日的な補償論を考えるべきだと主張。人々の価値観が財政を左右する。2018/07/30
ばぶでん
4
富裕層は圧倒的少数である以上、民主国家で国民が経済合理的に行動すれば過激な累進課税が実現される筈であり、特に最近は先進国でも中流層が崩壊し、国民格差が拡大していることからすれば猶更の筈である。しかし、現実には相続税廃止や所得税のフラット化が進むのは何故か考えると確かに奇妙である。著者は、平等取扱、支払能力、補償の観点から正義・公正な課税を論じ、先の世界大戦時において国民総力戦となって説得力を獲得した「富の徴兵」等の補償論の考え方が、近代兵器主体の少数兵員化で説得力を失ったことを挙げる。目から鱗が落ちた!2018/09/05
-

- 電子書籍
- 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君【分…
-
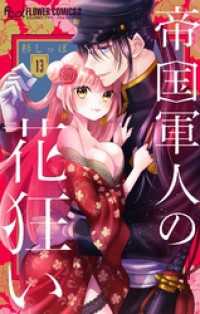
- 電子書籍
- 帝国軍人の花狂い【マイクロ】(13) …
-
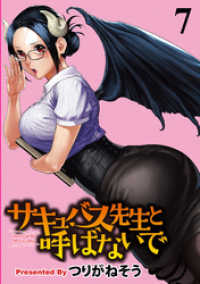
- 電子書籍
- サキュバス先生と呼ばないで WEBコミ…
-
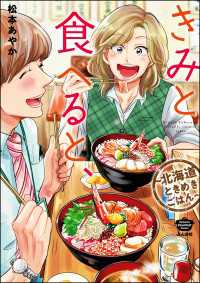
- 電子書籍
- きみと食べると、~北海道ときめきごはん~
-
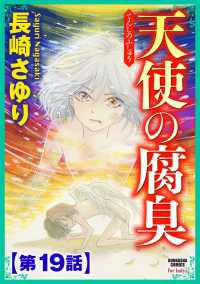
- 電子書籍
- 天使の腐臭(分冊版) 【第19話】




