内容説明
中村武羅夫が文壇に名を売り出すきっかけになったのは雑誌『新潮』に明治41年(1908)からほぼ毎月発表した「作家訪問記」でした。今日風にいえば「直撃取材」し、そこで得た個人的印象、いわば「独断と偏見」を臆面もなく堂々と記したことで、読者の反響を呼び起こしたのです。 本書はその連載を書籍化したもので、版元を変えながら刊行されつづけた隠れたベストセラーであり、明治の文壇を知る好資料です。
-

- 電子書籍
- 日露戦争物語(分冊版) 【第175話】…
-
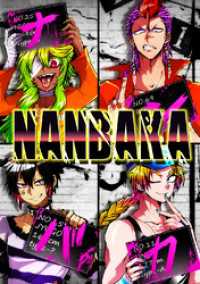
- 電子書籍
- ナンバカ 第401話【タテヨミ】
-
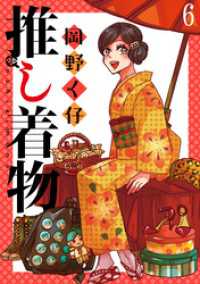
- 電子書籍
- 推し着物 ストーリアダッシュ連載版 第…
-

- 電子書籍
- ブスに花束を。【分冊版】 68 角川コ…
-

- 電子書籍
- 別れさせ屋の女~愛の断捨離しませんか?…



