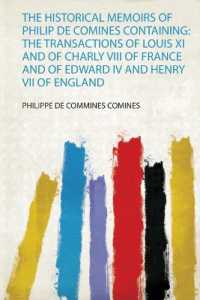- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
「なぜ優良企業は新世代の技術競争に敗れ去るのか?」
大御所経営学者のクリステンセン教授が『イノベーターのジレンマ』で答えたストーリーには未解決の問題があった。
長年解明されてこなかったイノベーションの謎に、若き経済学者が最先端のデータ分析で挑む。
「謎に対する答えだけでなく、ジレンマへの処方箋、さらには生き方のコツまで提示した本書は、21世紀を生きる我々にとって新たな羅針盤となる一冊だ。」(安田洋祐・大阪大学准教授)
●一時代を築いた「勝ち組」は、なぜ新世代の競争に出遅れがちなのか?
●この「イノベーターのジレンマ」に打ち勝つには、何をすべきなのか?
内外の企業が直面するこれらの切実な「問い」に、気鋭の経済学者・伊神満イェール大学准教授は、サバイバルの条件は創造的「自己」破壊にあり、と答える。
「共喰い」「抜け駆け」「能力格差」をキーワードに、ゲーム理論、データ分析などを駆使して、「イノベーターのジレンマ」をクリアに解明する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
91
クリステンセンの著書「イノベーションのジレンマ」を経済学的な観点からわかりやすく書かれたもので、私は楽しく読ませてもらいました。最近はマクロ経済学よりも企業行動の分析に目を向けたミクロ経済学的な分野で楽しませてくれる経済書が増えて来ているようです。デジタル的な分野で最近は「創造的破壊」ということがいわれてきていますが、時期がぴったりの良書でした。2018/12/20
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
32
「気軽なノリ」と著者自らが豪語するだけあり、めちゃめちゃ読みやすかった。 なんせ「経済学の初学者は、小難しい理論の話は斜め読みしてもいいし、ここは飛ばしても構いません」と言い添えてくれるので、理解できなくても罪悪感なく読み進められる。 (正直6,7,9章は所々斜め読みしました 笑) また、1章で本書全体のあらすじを示した上で都度振り返りを書いてくれているので、構成的にも親切だ。第8章「動学的感性を養おう」は、普段感覚でやっているコスト判断の数理的論拠を、親しみやすい話題で楽しく学べた。2020/01/27
RASCAL
21
既存企業によるイノベーションが新参企業よりも後れをとる理由を数理的な根拠を以て経済学的に説明した本。企業の意思決定のメカニズムに言及、トヨタがEVで日産に後れを取っている理由とか、現実の問題の推論に役に立つ。この本は、経済学は誰の役に立つのかということに焦点を当てている点が、単なる解説書と一線を画している。たとえ話は多少ピントを外れているものもあり、最後の2章はそれまでの丁寧な説明からやや飛躍気味だったが、学問のための学問ではない、世のため人のための学問とは何かについて考えさせられもした。2018/12/20
Francis
19
ある経済系の読書会で課題本となっていたので読んだ。私はどちらかと言えばマクロ経済学の方に興味があってこちらのミクロ、産業組織論には疎いのだけれども、今までの知識を思い出して大体納得できる内容だった。伊神さんの語り口が面白いのでサプライズを期待してしまうが、そう言うことはないです。企業や産業は政府が監督しない方が良い、と言うのは納得。2018/08/28
molysk
17
既存企業は、たとえ有能で戦略的で合理的であったとしても、新旧技術や事業間の「共喰い」がある限り、新参企業ほどにはイノベーションに本気になれない。さらに、「共喰い」を推進すれば、旧事業の資本は毀損して、「企業価値の最大化」という株主利益に反する可能性がある。また、現実のIT系産業の「創造的破壊」は、政府介入ではなく、「競争と技術革新のバランス」でもたらされた。だが、以上の結論に大した価値はなく、「どんなことを、どんな風に考えながらそこに到達したのか」という「道のり」こそが、大人に必要な「科学」というものだ。2019/02/24
-
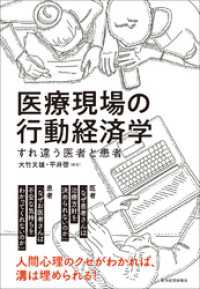
- 電子書籍
- 医療現場の行動経済学―すれ違う医者と患者