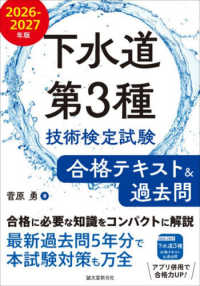- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
高齢化・人口減少といった社会構造の変化に直面しながらも、日本経済は低迷を脱して、本来の活力を取り戻しつつある。それは、多くの企業が“失われた10年”の間に、新しいビジネス環境に適合した「事業の再設計」に成功したからだ。まさに今、日本企業の前には、巨大な可能性が広がっている―。日本的経営論の原点となった名著『日本の経営』の著者で、「終身雇用」という言葉の生みの親であるアベグレンが、日本企業の過去数十年間の歩みを分析するとともに、これから進むべき方向を提言。半世紀におよぶ日本企業研究の集大成として書き下ろされた注目作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
96
日本の経営をむかし三種の神器で説明したが、この本は2004年に書かれたものでバブルがはじけて失われた10年ののちのことで日本を元気づけようと書かれた気がします。基本的な日本の経営を支えている原理は変わっていないということを再度日本の経営者たちからのヒアリングによって確認しているようです。やはり製造業が基本で発展途上国への産業の移転も生じますがそののちのための研究費を投資していくことも重要であると述べています。2016/02/23
Kiyoshi Utsugi
33
著者のアベグレン氏は、1958年に「日本の経営」という本を書いており、その中で日本的経営の特徴として終身の関係、年功序列制、企業内組合を初めて指摘された方です。 また、ボストン・コンサルティング・グループの設立に関わり、日本支社の初代代表を務めた方です。 50年前に書かれた「日本の経営」は、アメリカの研究者が読者として想定しているのに対して、今回の「新・日本の経営」は日本の企業関係者を読者として想定されているようです。 ただ、主張は当時から一貫しているとのことで、「日本の経営」も読みたくなりました。😀2023/06/08
手押し戦車
8
製造拠点を海外に移す時、空洞化と呼ばれるが陳腐化技術と労働集約型の仕事を海外に動かすだけで、空洞化は国内産業が停滞して高付加価値製品に移行して行けて無い時で、人件費が製造業にはアキレツケンになる。高付加価値のみ国内産業にして陳腐化したら海外に移し新たな資源を新技術に入れる攻撃的に知識を使う。製造業も知識集約型になり製造は海外にアウトソーシングして価格競争を避ける為にイノベーションが欠かせなくなる。知識が主役になると新陳代謝が早まる。2014/08/24
Yakmy
2
非合理的に見える日本の経営が、風土によって最適化された結果だと示している。改訂版だが、根底を貫くテーマは変わっていない。2016/11/20
半分白い
1
日本型経営を外からの目でとらえた著作。 今となっては古典だが、押さえておくべき本。2005/09/28
-
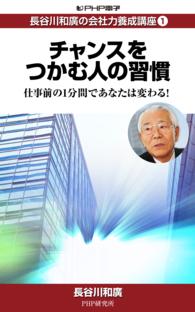
- 電子書籍
- 長谷川和廣の会社力養成講座1 チャンス…