- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
2018年3月19日、塔内一般公開を契機に、再び世間の耳目を集める《太陽の塔》。我が国最大の芸術作品にして最も知名度の高いパブリックアートだが、それを取り巻く数々の物語についてはほとんど知られていない。本書は、構想段階から現在にいたる太陽の塔の実相をさまざまな角度から取り上げ、単なる“巨大彫刻”との見方に終わらない《太陽の塔》の新しい鑑賞眼を養う種々の知見を提供する。岡本太郎の最高傑作はいかにして生まれたのか、万博会場でなにがあったのか、その後どんな運命をたどったのか──などを楽しく、わかりやすく解説していく。再生された内部、新規撮影のカラー口絵付き。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旗本多忙
22
70年の日本万国博覧会の時に建てられた太陽の搭。全ての建造物は閉会後直ちに撤去され、シンボルであったエキスポタワーも老朽し後年解体された。しかし永久保存となった太陽の搭は今も静かに鎮座しているのだ。その理由は?また太陽の搭とは何なんだ?なぜ岡本太郎が作ったのか?日本での最大で初のイベントだ万博は。必ず成功をと願い、多くの人の尽力がうかがえる。子供に万博の絵を描かすと皆が太陽の搭を描くらしい。そこまで何故愛されるのか?今後は万に1つもこのようなものは出現しないとか。太陽の搭は静かに宇宙を見つめている。 2021/03/09
ロビン
19
この秋、友人と太陽の塔を見にいけることになったので、気が早いけれど予習として一読した。思想編、実務編、展示編の3部構成で、太陽の塔について解説している一冊。「誇らかな、人間の尊厳を象徴」してつくられた太陽の塔だが、そもそもはテーマプロデューサーを任された太郎が「建築なきパビリオン」の施設機能を担保するメカニズムとして発案したもので、観客流動の課題に対処する解法として編み出されたものだったらしい。国家予算を使った太郎の自己主張とかでは全くないのだ。背中の「黒い太陽」も丹下健三の要望から描かれたという。2022/07/17
けい子
17
地下にある4つ目の顔「地底の太陽」が二代目と知る。当時の本物は兵庫県の自治体に寄贈されその後、行方不明との事。二代目を見ましたが、あの大きさで世界的に話題になった物が、何故そう簡単に行方不明になるのか?私はそこが気になった。絶対どこかにあるはず。2021/02/22
リュウジ
11
★5何を表しているのかわからない。奈良の大仏などと違って存在理由さえはっきりしない。その太陽の塔はどのようにして生まれたのか。この本で明かされるその経緯、そして太郎の情熱と哲学と考え方を知れば知るほど、スケールの大きさ、ち密さに驚かされる。オファーを何度も断りながらも、頭にあふれ出す創造をやめない芸術家としての性。その自分の創造をコトバ化する力。そのコトバをもって芸術家とは相反するプロデューサーとして国家的プロジェクトを推進していく見事さ。太郎があの時代にいたこと、太陽の塔が生まれ残されたのはまさに奇跡。2024/05/11
T.Y.
8
《太陽の塔》は元々大阪万博のシンボルタワーではなく、テーマ展示プロデューサーの岡本太郎に誰もそんなものを依頼してはいなかった。人の流れを処理するためのエスカレーターという役目から始まる塔の構想・建築過程、そこに込めた岡本の思想とその技法、そして万博後も残されるに至った経緯と現在の内部復元まで出版物・手稿・インタビューといった各種資料に基づいて辿る。太陽の塔だけでなく、パビリアンの展示内容や予算についても詳述、それが民博に繋がったことも。当時の人々が万博に賭けた意気と豪毅な決断もよく伝わる。優れた一冊。2018/09/27
-
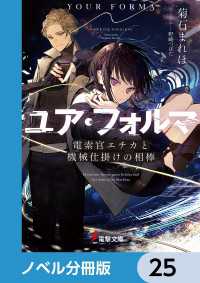
- 電子書籍
- ユア・フォルマ【ノベル分冊版】 25 …
-

- 電子書籍
- コミカライズ版 イケメン革命◆アリスと…
-

- 電子書籍
- 禁断Loversマニア Vol.045…
-

- 電子書籍
- 千のプラトー 合本版 資本主義と分裂症…
-

- 電子書籍
- 火曜日の手紙 ハヤカワ文庫NV




